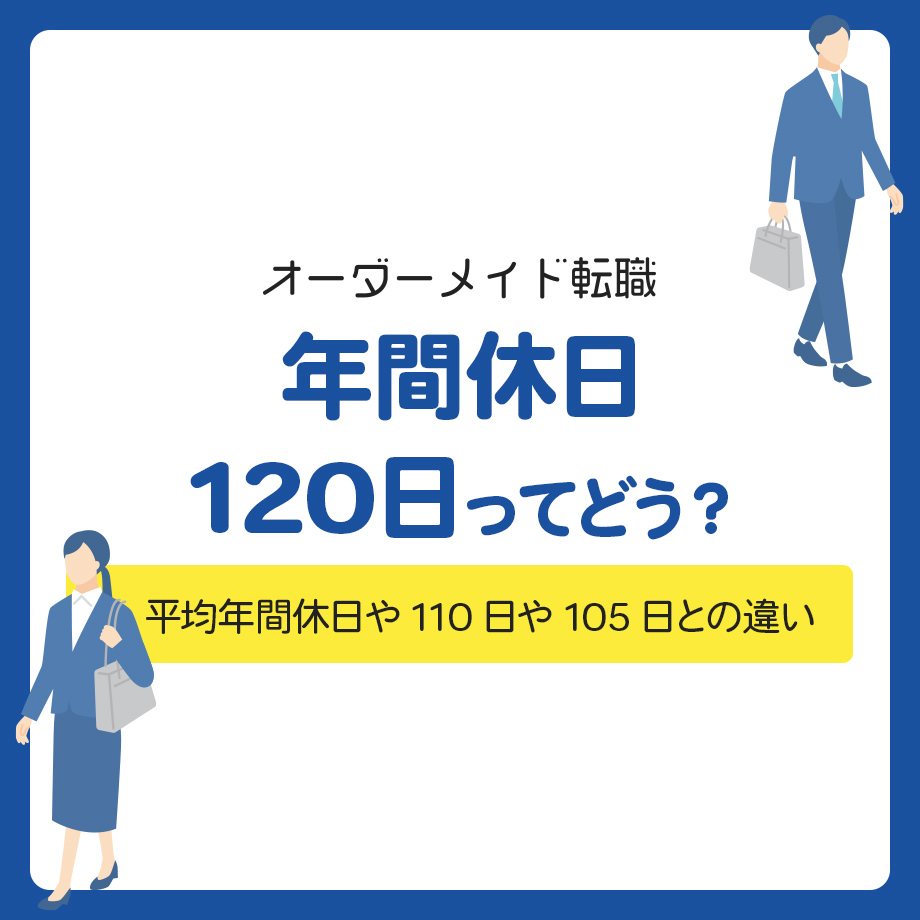
より理想的な働き方ができる職場を見つけたい時に、重視しておきたい要素の一つとなるのが年間休日数です。当然ながら各企業で休日の取り方には違いがあり、休みの多さも異なります。そこで各企業でどれくらい休みがあるのか、大まかな目安となるのが年間休日数です。漠然としたイメージで、「年間休日120日以上なら休みが多そう」などの印象は持っていても、実際のところはあまりピンと来ていない場合もあるでしょう。そこで今回は、「年間休日120日」における、休暇のパターン例を解説。あわせて平均的な休暇数や、よくある年間休日数ごとの休み方についてもご紹介します。
年間休日に数えられる休暇とは?
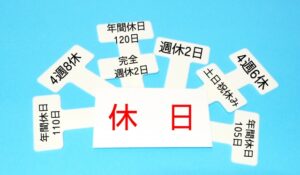
そもそも年間休日とは、各企業の規則として設定されている、休日の一年を通した合計数を指します。例えば「土日休み」であれば、毎月の公休をはじめ、会社全体での休業日なども含めて年間休日とされます。
仮に取得できるタイミングは一斉でなくても、お盆や年末年始などの連休が規則化されている場合、これらも年間休日として数えられます。シンプルに考えるなら、「毎月の公休+社内のルールで決められた他の休日(大型連休)」とイメージしておくとよいでしょう。
年間休日に有給休暇は含まれない
有給休暇は、一定の条件を満たす従業員に対しては、企業側が必ず与えなければならない休日です。ただし有給休暇に関しては、年間休日には数えません。有給休暇は付与義務のある休日ですが、従業員の判断で自由なタイミングと日数で取ることから、個々の取得状況に応じて変動するため年間休日数には含まないのが通常です。
さらに育休や産休などの法定で義務化されている休暇も、個人の状況に合わせて取得するため、年間休日数からは除かれます。その他にも、企業によっては「記念日休暇」や「リフレッシュ休暇」など、従業員の希望で取得できる独自の特別休暇を設けているケースも。こうした個人の希望制による特別休暇も、年間休日数には入りません。そのため年間を通した休暇の合計は、厳密には「年間休日+有給休暇+法定義務のある各種休暇+特別休暇」となります。
年間休日の平均日数は?
休みが多いか少ないかの判断基準として、なんとなく「年間休日120日」が目安になるイメージもあるかもしれません。なお厚生労働省の調査(※1)によれば、年間休日数の平均は、企業ベースで見てみると112.1日。労働者一人あたりの平均年間休日数は、116.4日となっています。このようなデータから考えるのであれば、「年間休日120日」は、平均よりも比較的多いといえるでしょう。
ちなみに年間休日数として、企業全体の35.8%が「120日~129日」としており、もっとも高い比率を占めています。次いで多かったのが「100日~109日」(28.4%)、「110日~119日」(22.0%)となりました。こうした点から見てみると、「年間休日120日」以上としている企業は多数存在していることが分かります。
「年間休日120日」で考えられる休日例

では「年間休日120日」となる場合に、どのように休暇が取れるのか、具体的な例も見ていきましょう。
まず「年間休日120日」を超えるケースでは、「完全週休2日」になるのが一般的。実際に計算してみると、次のように想定できます。
365日(年間)÷7日(1週間)=約52週(1週間の回数)
約52週×2日(毎週2日休み)=合計104日
「年間休日120日」であれば、「完全週休2日」として毎週の公休があっても、まだ余剰があることが分かります。
なお基本的には、この「完全週休2日」に祝日を加えると、「年間休日120日」前後になります。ちなみに2025年では一年のうち「19日」が祝日となっており、「完全週休2日」と合わせると、年間休日数は123日になります。こうして考えると「年間休日120日」では、どこかしらの祝日では一部出勤になる可能性はあるものの、原則は休みになるようなイメージです。
「年間休日110日」や「年間休日105日」ではどう変わる?
厚生労働省の調査結果でも出てきたように、年間休日「110日~119日」や「100日~109日」としている企業も多々見られます。そこで年間休日数として、よくあるのが「110日」や「105日」として設定しているケースです。では「年間休日110日」や「年間休日105日」では、どのような休み方になるのか、それぞれの大まかな目安も見ていきましょう。
年間休日110日の場合
毎週必ず2日休みになる「完全週休2日」のケースでは、その分だけで年間の休日数は合計104日となります。そのため「年間休日110日」では、「完全週休2日」に加えて、一部の祝日を休みとするパターンが多く見られます。
その他にもよくあるのは、祝日のある週の一部に限って、公休を1日にする例です。例えば「土日休み」の「年間休日110日」なら、「月曜が祝日になる前週の土曜は出勤」などのように調整する場合もあります。
もしくは「完全週休2日」ではあるものの、祝日は基本的に出勤として、残りの6日前後はGWやお盆などの連休に充てる休み方なども。「年間休日110日」では、「年間休日120日」に比べると多少休みは少なくなりますが、比較的無理なく働きやすい休み方ができるでしょう。
「年間休日105日」の場合
「完全週休2日」の毎週休みだけでも、合計すると年間休日数は104日となります。そのため「年間休日104日」では、「毎週2日休み」に限定されるか、もしくは「原則週1日休み+祝日や各種連休」などの休み方になるパターンがよく見られます。このように「年間休日105日」になると、「年間休日120日」に比べて、休みはかなり少なく感じる可能性が高いでしょう。また「週1日休み」などで年間の合計休日数を調整するケースもあるので、一定のリズムではなく、シフト制で休みが変動的になる場合も考えられます。
「年間休日120日」以上で想定される働き方のパターン
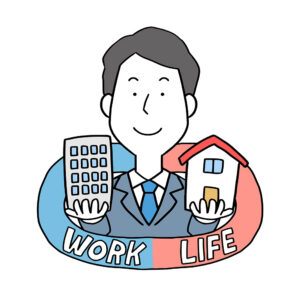
では「年間休日120日」以上の休みがあることで、実際にどのような働き方になるのか、具体的に想定される勤務形態のイメージも見ていきましょう。
毎週2日間の休みが取れる
「年間休日120日」以上になると、完全週休2日でも比較的余裕があり、毎週少なくとも2日間は休めることが想定されます。そのため「年間休日120日」以上では、「土日休み」になる場合も多くあります。また「土日休み」でないにしても、毎週決まった曜日で二連休になるケースもよく見られます。もちろん企業ごとに休みの設定方法は異なりますが、「年間休日120日」以上になれば、毎週の休日が一定になるパターンも多々あります。そのため決まったリズムで休みを取りやすく、比較的安定した働き方になりやすいのも、「年間休日120日」以上で見られる特徴です。
定期的な長期休暇がある
「年間休日120日」では、完全週休2日に加えて、年間のうちに16日前後の休暇を取ることができます。そのため16日前後分の休暇は、GW・お盆・年末年始などの大型連休に充てるケースも少なくありません。「年間休日120日」以上になれば、会社としての定期的な長期休暇があり、旅行などで余暇も満喫しながら働ける場合も多くあります。「年間休日120日」以上になると、しっかりとプライベートも充実させながら、十分にリフレッシュしつつ働ける可能性も高いといえます。
有給休暇と組み合わせて長めの連休にすることも
「年間休日120日」以上では、毎週少なくとも2日休みを設けていることが多く、公休として二連休が取れる場合も多々見られます。そのため二連休の前後で有給休暇を取得して、会社全体としての長期休暇に加えて、少し長めの休日を取れるケースも考えられます。有給休暇をうまく活用して二連休につなげて、プライベートの予定に応じて独自に長期休暇を作れる可能性が高いのも、「年間休日120日」以上の特徴です。
一日の勤務時間が長くなりやすいケースも
「年間休日120日」以上では、休暇が多めに取りやすい分、一日の勤務時間に響いてしまう可能性も考えられます。休日が多くなればなるほど、単純に出勤する日数は少なくなるため、効率的に業務を進めないと一日ごとの勤務時間が長くなってしまう場合もあります。出勤日数が限られてくる代わりに、一日ずつの生産性を意識しておかないと、結果的には残業が多いなどの働き方になるリスクもあるので注意が必要です。
充実の年間休日数に期待大!ホワイトな働き方がしやすい職種は?
では実際に、年間休日数が多くなりやすい、職業の一例をピックアップしてご紹介。厚生労働省による「令和6年就労条件総合調査」(※2)をもとに、平均年間休日120日前後となっている仕事をリストアップしていきます。
情報通信業(平均年間休日数121.3日)
(例)
通話サービス、携帯販売、放送関連、ソフトウェア開発、データベースサービス、マーケティング、サーバー運営、配信サービス、映像・音楽制作、新聞・出版 など
金融業、保険業(平均年間休日数120.7日)
(例)
銀行、信用金庫、クレジットカードサービス、証券会社、投資運用、信託会社、生命保険、損害保険、保険代理店 など
学術研究、専門・技術サービス業(平均年間休日数120.5日)
(例)
研究・開発機関、法律事務所、特許事務所、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所、デザイン事務所、作家・芸術家(小説家、画家、イラストレーター、作曲家他)、経営コンサルタント、興信所、翻訳・通訳、司会業、広告制作、設計事務所、測量事務所、写真撮影スタジオ など
電気・ガス・熱供給・水道業(平均年間休日数118.4日)
(例)
発電所、ガソリンスタンド、熱供給会社、地域冷暖房会社、水道局、浄水場、下水処理場 など
卸売業(平均年間休日数117.8日)
(例)
総合商社、貿易商社、専門商社(医薬品・化粧品、繊維・衣類、食料・飲料、魚介、食肉、野菜・果実 他)など
製造業 ※機械関連(平均年間休日数117.2日)
(例)
産業用機械・装置、生産用・業務用機械器具(建機、梱包機、金属加工機、医療器具 他)、電気機械器具、情報通信機械器具、輸送用機械器具 など
あくまで平均値のため、上記に挙げたもので必ず年間休日数が多くなるわけではありませんが、職場選びの際などには目安として参考にしてみてください。
まとめ
「年間休日120日」では、一般的には「完全週休2日+他の休暇」の休み方になりやすく、普段の公休以外の休日も十分に確保されやすいメリットがあります。さらに「年間休日125日」や「年間休日130日」になってくると、例えば「完全週休2日+祝日+定期の長期休暇」など、より充実した休暇が取れる可能性も高くなります。しっかりとプライベートも楽しめる働き方を重視したい場合には、「年間休日120日」を基準として、どのような休暇制度になっているのかチェックしてみるのがおすすめです。
