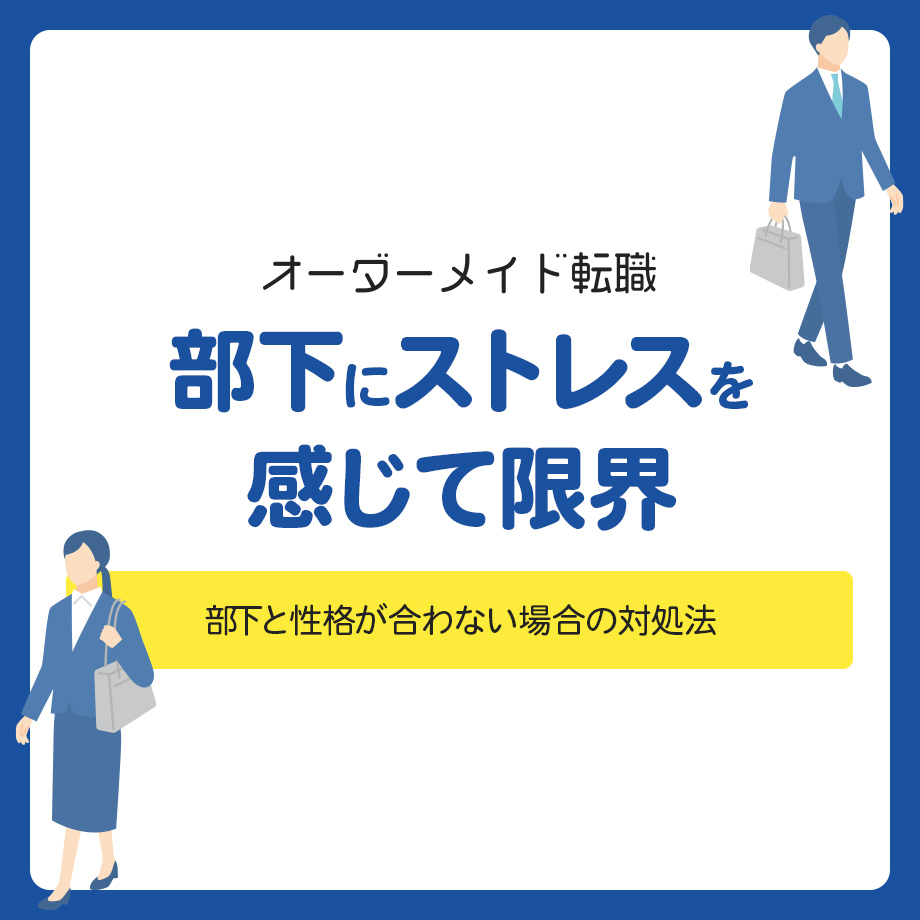
部下を持つ立場としては、職場内の人間関係を円滑にしてチームワークを高めるのも、大切な役割の一つ。とはいえ人と人との関わり合いのなかでは、どうしても苦手に感じてしまう相手は出てきてしまうものですし、それが部下のなかにいるケースも珍しくありません。場合によっては、「あの部下に指導したり仕事を振ったりするのが苦痛……」など、日々の業務に支障をきたしてしまうことも。さらに部下の存在が大きなストレスになっていると、自分自身のメンタル不調につながってしまう可能性もあります。そこで今回は、自分とは合わない部下との関係性に悩む場合に、職場内でできる対処法をご紹介していきます。
どんな部下を苦手に感じる?上司のストレスが限界になる時のパターン例

部下のなかにもさまざまな性格や価値観の人材がおり、上司としての精神的負担になりやすいパターンも幅広く存在します。あくまで代表的な例ですが、次のような傾向が見られる場合に、上司側がストレスを感じてしまうことが多々あります。
指示に従わない・言い訳が多いなどの反抗的な言動をする
何度も同じようなミスや質問を繰り返していて、仕事を覚えない
自発的に業務を進める気がなく、意欲が見られない
常に消極的な姿勢で、何を考えているのかわからない
報告・連絡・相談がなく勝手な判断で行動する
自分の欠点や課題を認めようとせず向上心がない
無断欠席・遅刻をするなど社会人としての基本的な自覚がない
上記以外にも、苦手に思ってしまう部下のタイプには、人それぞれで違いがあります。こうした苦手な部下がいるケースも含めて、人間関係に問題が発生している際には、まずは自分にとってどこまで許容範囲なのか見極めることも大切。何をされると嫌悪感を覚えてしまうのか、自分のなかで整理してみることで、どう接していくべきなのか見えやすくなります。
苦手な部下がいる時に考えたい対処法8選
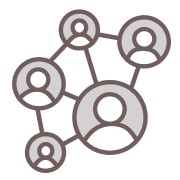
では実際に、苦手に思ってしまう部下がいる場合に、職場で実践できる対処法をいくつかご紹介していきます。
まずは自分自身の言動を見直してみる
苦手な相手だと思うと、どうしても言葉が厳しくなってしまうなど、無意識に態度が変わっているのもありがちです。大前提として、自分自身の言動が相手のマイナスな部分を引き出していないか、自らの普段の行動や発言を見直してみるのも重要。また的確なマネジメントができていないと、部下側の不平不満につながり、指示に背くなどの反抗的な態度や姿勢を招いている可能性もあります。例えば「わかりやすい指導ができているか」「チームのビジョンを共有できているか」「無理なノルマや目標は与えていないか」など、自らの管理体制を分析するのも大切です。
自分自身がマネジメントに専念できるようにする
自分だけで業務を抱えすぎると、自らに大きなストレスがかかることで、部下のマイナスな部分が見えやすくなったり相手の態度を悪化させてしまったりなどの問題も起きやすくなります。近年は人手不足の影響から、マネジメントだけでなく、現場業務も含めて幅広く担当している管理職も増えてきています。このように日頃の負担が大きいことで、管理業務に集中できず、部下からの不満につながるマネジメントになっているケースも。むしろ部下でも対応できる業務を割り振らないと、相手からしてみれば自分は信用されていないと感じてしまい、あまりよくない態度や言動が出てしまうこともあります。自らで担当できる範囲が広いと、「自分でやったほうが早い」と思いがちですが、そこをぐっとこらえて部下に業務を渡すのも大事。こうして自分の仕事の負担を軽減すれば、自らの管理業務にリソースを割くことができ、マネジメントの質を高めて部下のモチベーションや納得感を生み出しやすくなります。そうすることで、部下側の態度や姿勢が改善され、良好な関係構築ができる場合もあります。
もう少し深いコミュニケーションができるように工夫する
嫌いな部下がいる時には、相手に対する理解が不足していることから、苦手に感じてしまっている可能性も考えられます。一方的に偏った視点で見てしまっている場合もあるため、まずは苦手だと感じる部下について、どのような人材なのかあらためて認識し直すことも重要です。特にコミュニケーションが足りていないと、その部下のよさをうまく引き出せていないことが多く見られます。そりが合わないように思えるかもしれませんが、上司側から歩み寄ることで、苦手意識が軽減されるケースも。例えば1on1やランチ会など、あえて親睦を深める機会を設けてみるのも一つの方法です。しっかりと交流していくことで、上司側も部下側もお互いの見方が変わり、関係性が改善される場合もあります。
苦手な部下こそ十分な観察・分析をしてみる
なぜ上司側として苦手だと感じてしまうのか、まずは部下のどのような部分が合わないのか内省してみるのも大切。そのうえで、なぜ上司の自分が苦手に思えるような言動になってしまうのか、部下の現状が生まれる原因を深掘りしていくとよいでしょう。
よくよく観察してみれば、部下自身にあるストレスから、上司に対する態度が悪化している可能性も。場合によっては上司と部下としての相性ではなく、別で抱えている相手側の不満や問題から、自分からは悪く見えるような発言や行動などにつながっているケースもあります。例えば「全然仕事ができない」と感じる部下がいたとして、詳しく話を聞いてみたら、今まで割り当てていた業務が適していなかっただけのパターンも。「少し異なる分野を任せたら、スムーズに対応できそうだった」というようなこともあります。また自分にきつく当たる部下がいたとしても、「希望の配属ではない現状に納得できていない」など、上司に関係ない点で不服に思っていることもあるでしょう。まずはしっかりと部下に対する理解を深めることで、上司として何をすべきなのか、的確な解決策が見つかるヒントになります。
アンガーマネジメントを実践する
苦手だったり嫌いに思えたりする相手には、誰もがついつい感情的になりがちです。だからといって衝動に任せて叱責するなどの行為は、さらに関係性を悪化させるうえに、場合によってはパワハラに該当してしまう危険性もあります。そこで苦手な部下と接する際には、アンガーマネジメントの実践を心がけてみるのもおすすめ。アンガーマネジメントとは、怒りを覚えた時に6秒間数えながら深呼吸して待つことで、気持ちを落ち着かせるものです。こうしたアンガーマネジメントにより、冷静な状況判断ができ、部下に対する見方もフラットになりやすい効果が見込めます。このように感情のコントロールをしていくことで、苦手な部下への意識が改善されるケースも。また感情に左右されない言動により、部下からの信頼が得やすくなり、相手側の態度が軟化して関係性がよくなる可能性もあります。
ポジティブフィードバックを意識する
ポジティブフィードバックとは、相手のよかった点や功績などの前向きな評価に注目し、肯定的な意見やアドバイスをかけるものです。こうしたポジティブフィードバックにより、部下側としても上司から認められる自信につながり、反抗的な態度や消極的な姿勢などが改善されるケースも見られます。また上司側としても、部下の長所や強みに目を向けることで、苦手意識が緩和される場合もあります。部下に対する見方や日頃の言動の捉え方を変えることで、自分自身の気持ちが軽くなり、良好な関係性を築ける可能性も考えられます。
自分よりも相性がよさそうな同僚などに任せる
どうしてもそりが合わなかったり、なかなか関係性が改善されなかったりする時には、ほどよく距離を置けるようにしたほうがよい場合もあります。「指示をしない」など、相手の存在を無視するような対応はもちろん言語道断ですが、接し方を変えられるように工夫してみるのも大事。そこで苦手な部下に対しては、自分よりも相性のよさそうな人材を教育担当にして、少し遠巻きにマネジメントや育成ができるようにする手段もあります。たとえ自分にとっては苦手な部下でも、別の誰かにとっては、きちんと良好な関係が築ける相手となる可能性も。その苦手な部下に対して、もし自分以外にうまく接することができそうな同僚などがいれば、頼りにしてみる方法もあります。チーム編成や業務分担を工夫して、苦手な部下との組み合わせがよくなる教育担当がつくように、調整していくことも検討してみましょう。
人員配置を変えられるように相談してみる
現状のままでは改善されそうな見込みがなければ、人事や自身の上長などに相談して、苦手な部下の人員配置を変えてもらう方法もあります。例えば「自分以外に対しても攻撃的」「他のメンバーも困っていて解決できない」など、上司としての対応を見直しても解消されない時には、配置転換を検討したほうがいい可能性も。所属している部署やチーム全体との相性があまりよくない場合もあるため、どうしても解消できなさそうであれば、まずは人事や自身の上長に話をしてみるのもおすすめです。
まとめ
仕事に限らず、どのような場面でも人付き合いにおける相性のレベル感は、組み合わせ次第で大きく異なるもの。そもそも部下側に問題があるケースもありますが、単純に相性が合わないだけの場合も見られます。状況に応じて対処法も変わってくるので、部下に対するストレスが蓄積されている時には、まずは現状をしっかりと把握していくのも大切。部下への大きなストレスを感じる際には、本記事も参考に、自分も相手も含めて何が問題なのか見直したうえで解決策を検討してみてください。
