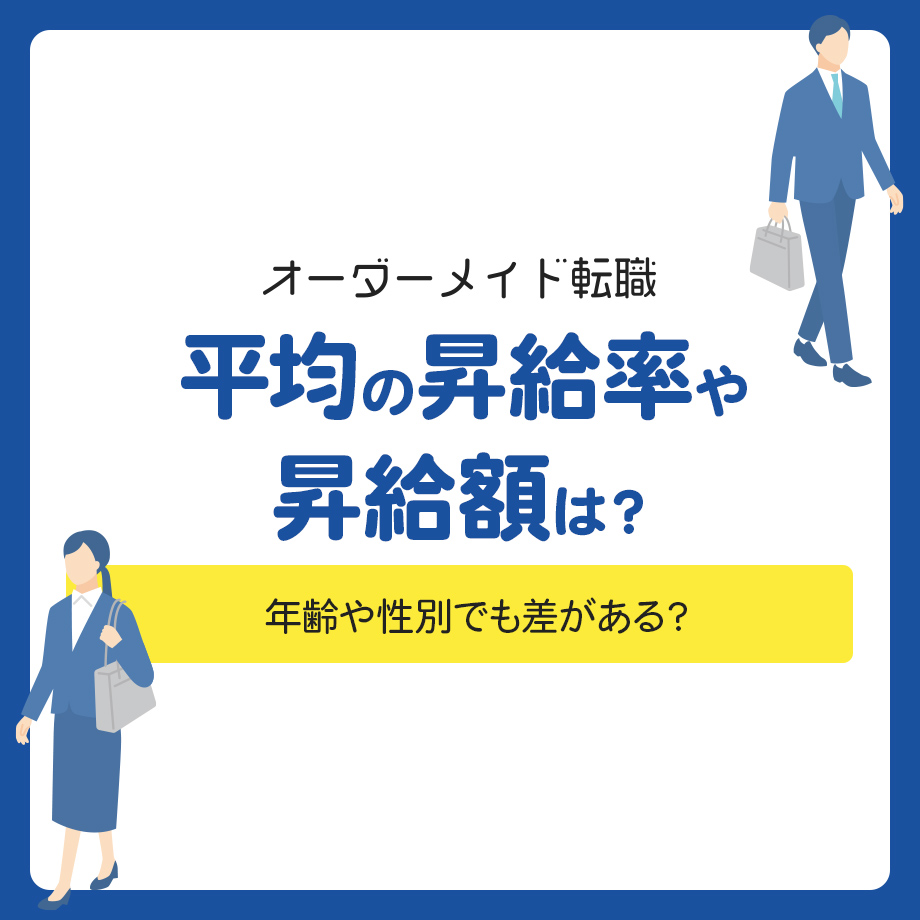
将来的にも長くキャリアを積んでいくにあたり、一般的にはどれくらい給与が上がっていくのか気になるもの。また今後も長年勤続していくことを考えるなら、全国的な平均に比べて、今の職場の昇給水準がどれくらいなのか知りたいと感じている場合もあるでしょう。そこで今回は、昇給の比率や金額の相場について解説。年齢・男女別に見た昇給の傾向なども含めて、詳しくご紹介していきます。
昇給には大きく分けて3つの種類がある

大前提として、昇給とは各企業の定める評価基準や社内規定などにより、元々設定された毎月の基本給(月給・日給・時給)から金額が上がっていく制度を指します。企業によって異なりますが、例えば年単位で前年よりも高い基本給に改定され、年収アップを目指していけるのが昇給です。なお昇給の仕組みとしては、大まかに次のような3つの種類に分けられます。
査定昇給
例えば成果・実績・目標達成率といった、各従業員の業務成績や能力などにともない、基本給の金額アップを目指せるのが一般的な昇給です。基本的には各企業で設定している判断基準をもとに、昇給の金額や比率が決められており、実力に応じて給与が上がっていきます。こうした昇給では、企業からの評価によって基本給が変動するため、従業員ごとに給与の上がり方も異なります。個人の努力や結果次第で、より高い収入につなげていくことができるので、仕事に対するモチベーションや満足感が得やすいのも特徴です。
定期昇給
定期昇給は、勤続年数や年齢に合わせて、一定期間ごとに必ず基本給が増額される仕組みを指します。厳密には査定昇給のケースでも、年単位や月単位などの一定期間の評価で給与が改定される際には、定期昇給と呼ぶこともあります。ただし近年では、年功序列や終身雇用の概念が見直されている傾向が見られています。こうした背景から、勤続年数や年齢によって自動的に昇給する意味合いで、定期昇給との言葉が使われる場合も。求人広告などでは、実力に応じて基本給が上がる査定昇給との使い分けとして、年を追うごとに給与が高くなる制度を定期昇給と示すことも多々見られます。なお勤続年数や年齢ごとに給与も上がる定期昇給では、長く働いたら働いた分だけ、収入アップにつながる特徴もあります。
ベースアップ
ベースアップとは、社内全体としての賃金アップを実施して、従業員全員の基本給を高くする昇給制度を指します。各従業員の実力や社歴など、個人ごとの状況には関係なく、企業としての給与水準を高くするのがベースアップです。例えば政府による、毎年の最低賃金の改定にともない、法令順守として社内の給与水準の見直しがおこなわれるケースも珍しくありません。こうした際に、社内全体の賃金のバランスを取る目的などで、ベースアップを実施する場合もあります。もちろんこのような法改正に限らず、会社の業績・社会情勢・経済状況など、さまざまな要因からベースアップがおこなわれます。
昇給の金額や比率の平均は?
厚生労働省の調査(※1)によると、2024年に従業員の賃金の引き上げをした企業では、1人あたり平均1万2,183円の昇給が実施されたとの結果が出ています。ちなみに昇給率は、1人につき平均4.1%。なお昇給をおこなった企業の割合は91.2%となっており、多くの職場で賃金の引き上げをしていることがわかりました。
(※1) 厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」
大企業と中小企業で違いはある?
同じく厚生労働省による調査(※1)では、企業規模別の昇給実施率・金額も発表されています。まず昇給をおこなった割合としては、次のような傾向が見られました。
従業員数5,000名以上:99.1%
従業員数1,000名~4,999名:93.5%
従業員数999名~300名:93.4%
従業員数100名~299名:90.2%
大企業と中小企業の双方ともに、賃金の引き上げをした比率は9割を超えており、昇給を意識している会社が多くなっています。さらに企業規模別の昇給金額の平均は、以下のとおりです。
従業員数5,000名以上:1万5,121円(平均4.8%アップ)
従業員数1,000名~4,999名:1万2,317(平均4.1%アップ)
従業員数999名~300名:1万618円(平均3.8%アップ)
従業員数100名~299名:1万228円(平均3.7%アップ)
昇給金額に関しては、上記にもあるように、企業規模が大きくなるにつれて引き上げ率が高くなりやすい傾向にあります。いずれも平均して1万円台の昇給がおこなわれていますが、従業員数5,000名以上の大企業になると、1,000名未満の会社に比べて1.5倍近くの賃金引き上げがされている結果となりました。
(※1) 厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」
昇給しやすい業種は?

企業規模による、平均的な昇給の金額や比率の差も見られましたが、業種で分けてみた場合にも違いが出てきます。なお平均昇給額・比率が高い業種としては、次のような例が挙げられます。(※1)
金融業・保険業/1万5,465円
建設業/1万5,283円
情報通信業/1万4,989円
学術研究・専門・技術サービス業(各種士業やデザイン・芸術など)/1万4,772円
電気・ガス・熱供給・水道業/1万4,619円
鉱業・採石業・砂利採取業/1万4,616円
製造業 /1万3,262円
不動産業・物品賃貸業/1万2,554円
いずれも平均昇給額を上回っており、給与アップを目指しやすい傾向が見られています。
(※1) 厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」
年齢別で見た場合には20代~30代の昇給率が高め
厚生労働省の発表(※2)では、世代ごとの毎月の平均賃金を見てみると、次のように変動しています。
20歳~24歳/約23万2,500円
25歳~29歳/約26万7,200円
30歳~34歳/約29万9,500円
35歳~39歳/約32万8,700円
40歳~44歳/約35万1,400円
45歳~49歳/約37万2,700円
50歳~54歳/約38万400円
55歳~59歳/約392万円
60歳~64歳/約31万7,700円
上記から考えると、「20代前半~後半」にかけて、もっとも昇給率が高くなっていることがわかります。次いで、「20代後半~30代前半」「30代前半~後半」と、比較的昇給している比率が高いデータもうかがえます。こうした賃金推移の傾向から、特に20代~30代にかけて、大きく昇給しやすい風潮にあるといえます。
(※2) 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
昇給の傾向は男女でも異なる
年齢別の毎月の平均賃金について、男女それぞれに分けて見てみた場合、次のような差が出ています。(※2)
【男性】
20歳~24歳/約23万4,200円
25歳~29歳/約27万4,700円
30歳~34歳/約31万6,300円
35歳~39歳/約35万2,300円
40歳~44歳/約38万5,500円
45歳~49歳/約41万6,000円
50歳~54歳/約42万8,200円
55歳~59歳/約44万4,100円
60歳~64歳/約34万4,700円
【女性】
20歳~24歳/約23万600円
25歳~29歳/約25万8,100円
30歳~34歳/約27万1,600円
35歳~39歳/約28万4,300円
40歳~44歳/約28万8,400円
45歳~49歳/約29万8,000円
50歳~54歳/約29万5,400円
55歳~59歳/約29万4,000万円
60歳~64歳/約25万9,900円
上記のデータから考えると、男性では「20代後半~30代前半」で、大幅に賃金が高くなる傾向にあります。一方で女性のみに分けてみると、大きな賃金アップが見られたのは、「20代前半~後半」。「20代後半~30代前半」でも、比較的昇給率は高い様子がうかがえますが、男性よりも賃金上昇は抑えめになっています。とはいえいずれにしても、20代~30代の若年層で給与が上がりやすいといえます。
(※2) 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
昇給の金額・比率を高めるポイント

もちろん各企業が定める制度の内容によって変わってくる部分もありますが、場合によっては、自ら昇給の金額や比率を高める工夫ができるケースも考えられます。できるだけ大幅な昇給を目指したいのであれば、次のような方法を検討してみるのもおすすめです。
スキルやポジションの向上を目指す
例えば担当の業務範囲が広がったり、達成できる数値目標が高まったりなど、スキルアップによって大きく昇給できるケースも少なくありません。評価による査定昇給であれば、自分の能力や成果次第で、給与アップを図ることができる可能性は十分に考えられます。なかには、業務に関連する資格を取ることで、基本給に別途手当が加算される場合も。このようにスキルに応じた手当によって、昇給に直結することもあります。また大幅な昇給につながりやすいのは、やはり新たに役職に就くなどのポジショニングです。昇格にともなう昇給は定番のパターンで、なおかつ管理職としての実力が認められるからこそ、給与の上がり方が大きくなっていることも珍しくありません。このように自分自身の積極的な行動から、大幅な昇給を目指せるチャンスもあります。
上司や先輩、人事担当に相談してみる
もし昇給に向けた判断基準が明確に認識できていなければ、上司・先輩・人事担当に相談してみるのも、一つの方法です。あまり昇給できていないと感じている際には、場合によっては、社内の昇給基準に沿った動きができていない可能性も考えられます。例えば、何をしたら給与アップにつながるのか・どのような成果が評価されやすいのかなど、昇給に向けてどう行動すべきなのかアドバイスをもらえるケースも。より大幅な給与アップを目指したいのであれば、まずはどういった昇給基準があるのか把握して、具体的な対策を考えてみるのもよいでしょう。
給与水準の高い企業に転職する
現職のまま昇給を目指すのが難しそうであれば、今よりも給与水準の高い企業への転職を検討してみる方法もあります。給与水準は企業によって異なるため、これまでに培ってきた経験や能力を活かしながら、勤務先次第では現在よりも高い収入を目指せるチャンスも。もしくは新たな分野にチャレンジすることで、最初はさほど高い給与ではなくても、将来的には大幅な昇給につながっていく可能性も想定されます。業種などによっても、平均的な昇給額や比率は変わってくるので、給与アップが狙いやすい分野に挑戦してみる手段も考えられるでしょう。
まとめ
昇給する仕組みは企業ごとに大きく異なるもので、例えば能力や勤続年数など、給与アップにつながる基準にも違いがあります。今回は、平均的な昇給の大まかな傾向などを見てきましたが、あくまで世間的な相場なので一概にはいえません。もし現職で給与アップを図りたいのであれば、まずは社内における昇給の規定などを確認してみるのがおすすめ。そのうえで詳細がわからなければ、上司や先輩などに聞いてみて、どう昇給していくのか認識してみるのがいいかもしれません。または、もし今回見てきたような平均から大きく外れるようであれば、場合によっては転職を考えてみるのも一つの方法でしょう。ぜひ本記事も参考にしつつ、今後どのように昇給を目指すべきなのか、検討してみてください。
