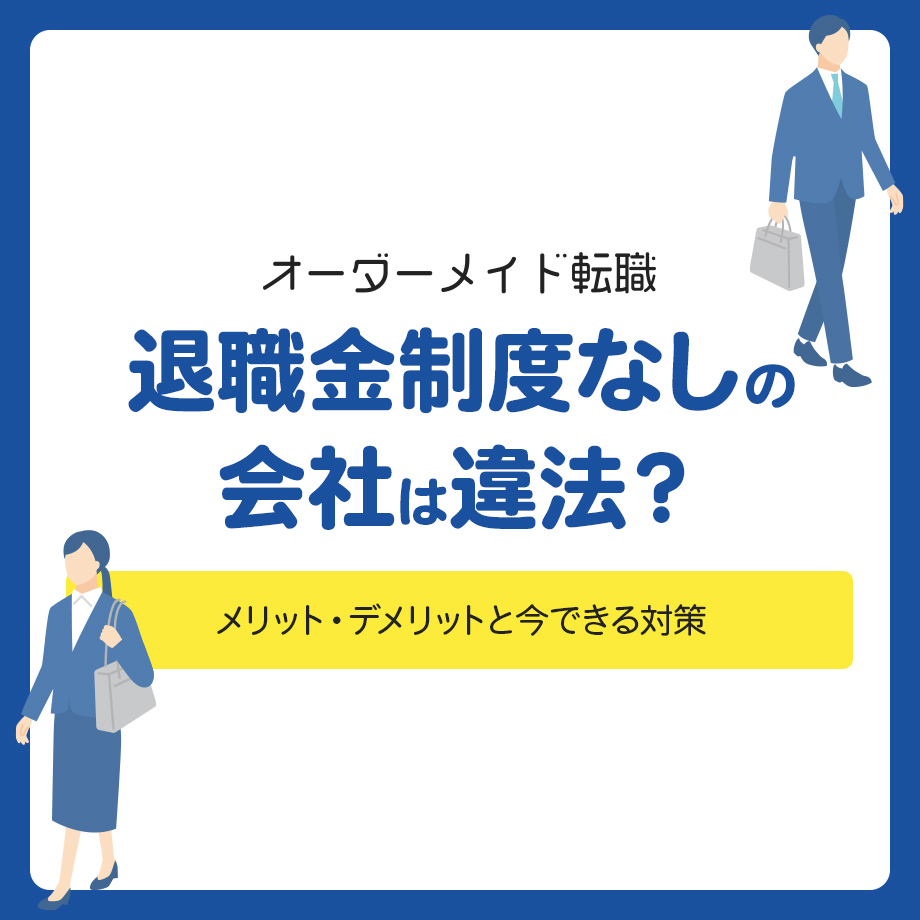
新たに就職先を決める際には、例えば給与や休日などのさまざまな労働条件は、自身の生活基盤にも深く関わるからこそ十分にチェックしておきたいポイントでしょう。企業ごとに待遇面は大きく異なるなかで、きちんと将来を見据えて長く続けていこうと考えるなら、老後の大切な備えにもなる退職金制度の有無も気になる部分かもしれません。退職金は、従業員に対する経済面の補てんや労いなどの目的で支給されるものですが、制度自体がないからといって必ずしもマイナスに影響するわけではありません。そこで今回は、退職金制度の実態からメリット・デメリット、支給されない時に考えておきたい対策まで解説していきます。
退職金制度に法的な義務はない

毎月の給与などの賃金とは異なり、退職金は必ず支払わなければならない法律上の規定はありません。退職金を出すかどうかは、各企業の自由な判断で決定できるので、社内の制度としてなくても違法にはならないのが基本です。ただし社内のルールとして、退職金制度が設定されている場合、不当に支払われなければ違法となるケースもあります。例えば就業規則・労働協約・労働条件通知書などで、退職金制度に関して明示している際には、企業側には支払う義務が生じます。とはいえ退職金の運用方法は、企業ごとの裁量次第で変わってくる部分もあり、制度そのものはあっても支給されないパターンも。退職金制度の内容は、あらかじめ詳細まで十分に確認しておく必要があります。
退職金がもらえるかどうかは勤務状況で変わるケースもある
退職金制度を取り入れている企業では、一定の支給条件を設けている場合が多く見られます。よくあるのが、勤続年数や労働時間・日数などに応じて、支払いの有無が変わってくるパターンです。なかでも勤続年数に関しては、「入社から3年以上」としているケースが多数。そのため働きはじめて、まだ日が浅いうちに辞めてしまうと、退職金が出ないこともあります。また労働時間・日数などの勤務形態によって、退職金の支給条件が異なることも多々あり、「フルタイムで働く正社員には出ても、パートやアルバイトには適用されない」などの例も。退職金制度がある際には、どのように適用されるのか、事前に把握しておくことも重要です。
退職金制度の有無は企業規模や業種によって異なる傾向も見られる
実際の退職金制度の運用状況としては、厚生労働省の調査(※1)によると、約7割の企業で支給しているとのデータが出ています。
また同様の調査では、企業規模ごとに比率が異なる結果も出ています。具体的には、従業員数1,000名以上で約9割、100名以上で約8割、30名以上で約7割と、企業規模が大きくなるにつれて退職金の支給率が高まっています。
さらに退職金の支給率は業種別でも違いが見られ、9割を超えているのが、おもに「鉱業・採石業・砂利採取業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「金融業・保険業」。その他にも、「建設業」「製造業」「学術研究・専門・技術サービス業」「教育・学習支援業」では、8割以上の高い支給率が見られました。
一方で「宿泊業・飲食サービス業」や「その他サービス業」では、退職金を出している企業は半数前後。業界全体として、退職金制度があまり使われにくい傾向が見られるようです。
退職金はもらえなくてもいい?制度がない場合のメリット
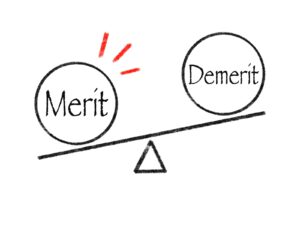
退職金制度がないと、あまり待遇がよくないイメージに見えてしまうかもしれませんが、一概にもそうとはいいきれません。退職金制度がないからこそ、得られるメリットもいくつかあります。では実際に退職金がないことで、具体的にはどのような利点が想定されるのか、以下から詳しく見ていきましょう。
退職金の代わりに毎月の給与や福利厚生が充実している
退職金制度として明示していないものの、代わりとして毎月の給与に上乗せしていたり、手当などの福利厚生で還元していたりする場合もあります。退職金制度自体はなくても、待遇面を総合して見てみれば、十分にカバーできているケースは少なくありません。例えば、基本給や賞与などの金額が業界相場よりも高かったり、住宅補助などの生活費に関する支援が手厚かったりするパターンも多々見られます。退職金制度がない時には、待遇全体をトータルして、その代わりになるほどの条件になっているか確認してみましょう。
辞める時期を問わず確かな収入が得やすい
一般的に退職金の金額は、例えば「毎月の賃金×〇年分」というように、各従業員の基本給を基準として各企業で定めたルールなどに従って計算されます。そこで多くの場合に見られるのが、勤続年数の長さに応じて金額が上がっていくパターンです。こうした退職金制度では、従業員側の転職回数が多いと、各勤務先の勤続年数が自動的に短くなって受け取れる金額が減ってしまうことも。一方で制度自体はなくても、もし基本給に上乗せして支給される場合なら、辞めるタイミングに関係なく必ず毎月少しずつでも退職金分がもらえることになります。仮にまた次に転職する時が来ても、あらかじめ毎月の給与に含めて働いた年数分の退職金を受け取れるため、「勤続年数が短くてもらえなかった」などの損をする心配もありません。
自分なりのペースで安定した老後資金を形成できる
退職金制度では、企業ごとに決められた算出方法にしたがって、最終的にまとまった金額を支給してもらえるのが基本です。このように退職金の金額は、各企業の判断によって変わってくるため、場合によっては思うような金額が受け取れないことも。例えば勤務期間中に、企業の業績悪化が起きた時など、資金の確保が難しいと退職金が減額される可能性もあります。このように退職金は、会社の都合次第で、将来的に受け取ることができる金額が変動する一面も。そこで退職金を頼りにするのではなく、自分自身で老後資金を作るようにしておけば、勤務先の事情に左右されることはありません。自ら貯金額などの調整も自由にできるため、「○歳の時点で□万円はあってほしい」というように、自分なりの目標に向けて着実に老後資金を形成しやすい利点があります。退職金だけを老後資金と考えてしまうと、想定するほどの金額がもらえないリスクもあるので、自らで蓄えをしておくと将来的な安心にもつながりやすいでしょう。
退職金制度がない時に気を付けておきたいデメリット
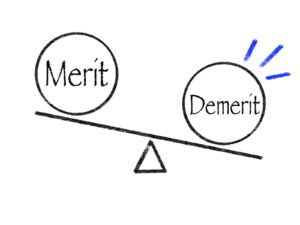
退職金は、各企業にとって支払う義務があるわけではなく、場合によっては支給しない分を事業資金などに回すケースもあります。そもそも退職金にする資金を確保しない方針の企業も少なくないため、もし制度がないようであれば、特に次のような部分には注意しましょう。
十分な自己管理をしながら将来に備えておく必要がある
退職金制度があれば、将来的にまとまった資金として、老後の蓄えの足しにできます。一方で退職金がない場合には、例えば定年を迎えて今までの仕事を辞めても、問題なく生活できるように自らある程度の備えをしておく必要があります。後々に退職金を受け取れない分、普段の給与を日ごろからしっかりと管理して、仕事を辞めてからの収入ダウンや緊急時などに対応できる資金を作っておかなければなりません。
万が一の緊急事態に向けた家族のための対策が求められるケースも
退職金制度がある場合、万が一にも支給対象の従業員が亡くなってしまった時には、その分を遺族に支払う死亡退職金を並行して取り入れているケースが多々見られます。そのため退職金制度があれば、自分の家族に対する死亡保障ができることも多く、緊急事態の備えにもできる一面があります。もし退職金制度がなければ、こうした死亡保障もないことになるため、非常時に向けて自ら対策しておかなければなりません。経済的な支えや扶養が必要な家族がいる際には、例えば生命保険など、何かあった時にも対応できる方法を検討しておくのも重要です。
先を見据えて長期的に勤続していくモチベーションになりにくい
退職金制度では、何年も勤続した分の功績から、まとまった高額な資金をもらえるケースが一般的です。こうした退職金による今後の大きなプラスがあると考えると、「せっかくなら将来のためにもっと長く頑張ろう」などの意欲も湧きやすいでしょう。しかし退職金がないと、長年勤続する目的要素が多少なりとも少なくなるため、同じ会社で続けていこうとするモチベーションが下がりやすい一面もあります。ある意味では退職金が目標の一つにもなり得るので、制度がない分、何か別に自らの気力につながるものを見つけておくことも大切です。
勤務先で退職金制度がない場合に検討しておきたい対策方法
もし今の職場や転職先に退職金制度がなく、将来的な不安を感じるのであれば、次のような方法で今後の備えができるようにしておくのもおすすめです。
自分で金額を決めて定期的に貯金していく
オーソドックスな方法ではありますが、例えば「毎月の給与の○割」「ボーナスはまとめて貯めておく」など、自分なりのルールを決めて貯金しておくのが無難です。銀行口座に預金しておけば、かなり少なめではありますが金利分を増やしていくことができ、もし急な出費があっても引き出しやすい利点もあります。また定期預金にすれば、満期までの引き出しは原則できませんが、通常の銀行口座に預けるよりも少し高い金利で貯めていくことも可能です。多少でもコツコツと長期間で貯めていくことで、将来的にはまとまった蓄えにできます。
資産形成に向けた各種サービスを活用する
退職金制度がない時には、少しずつ資金を投入しながら、運用して金額を増やせる資産形成の各種サービスを使ってみるのもいい方法です。代表的な例として、個人年金保険・iDeCo(個人型確定拠出年金)・NISAなどで、将来的な年金の足しとして活用されています。ただしこうした資産形成サービスは、一定期間まで投入したお金を引き出せなかったり、元本割れが発生したりなどのリスクもある部分を含めて検討してみましょう。
退職金制度が用意されている企業に転職する
もし現状の待遇にあまり満足できていないようであれば、退職金制度がある企業への転職を考える方法もあります。「現時点の給与では貯蓄ができない」などの場合には、老後の備えとして、将来的に退職金制度が適用される転職先を見つけたほうが無難かもしれません。今の職場における待遇面を整理しつつ、退職金制度も含めて、経済的に安心できそうな転職先を検討してみるのも一つの手段です。
まとめ
退職金制度では将来的にまとまった資金として受け取ることができ、今後の蓄えにもなるものですが、企業によっては待遇として設けられていないケースもあります。ただし退職金の運用方法は、企業ごとに異なり、制度自体はなくても実質的な収入として受け取れる仕組みになっている場合も。もし退職金制度がなければ、他の待遇面と合わせて、総合的に見たうえで自分自身の経済面に問題がないかチェックしてみましょう。また退職金制度がなくても、この先の金銭的な備えをしていく方法はいくつもあります。退職金も含めてこの先の備えを考える際には、ぜひ本記事も参考に、老後資金の形成について検討してみてください。
