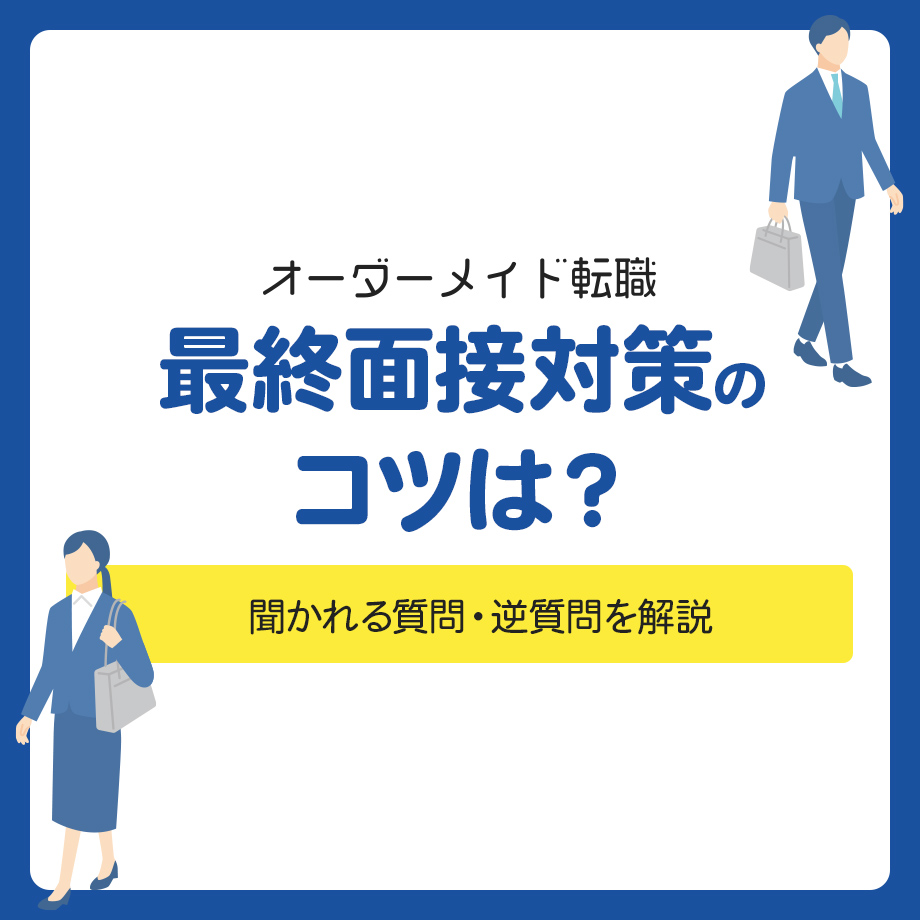
一般的に最終面接の前段階では、各人材がこれまでに培ってきた経験・スキルや適性など、社内の実務や労働環境との相性を見極めるケースが多く見られます。それに比べて最終面接は、企業側にとっては、採用するかどうか最後の判断を下す、いわば決め手となるもの。だからこそ、自社の理念やビジョンに合致した人材なのか、重要な質問をされるのが基本です。そこで今回は内定につながる最終面接にするために、あらかじめ備えておきたい対策をはじめ、よくある質問や逆質問に使える回答例を解説していきます。
最終面接で重視されやすいポイント
基本的に一次面接や二次面接は、人事担当・部門リーダー・部署の管理職など、比較的現場に近いポジションで実施されやすい傾向にあります。一方で最終面接は、直接的な採用の決裁権を持つ、代表や役員などの経営陣が担当する場合が多く見られます。自社にとってどのような利益をもたらすのか、事業の成長にどう貢献してくれる人物なのか見極めるためにも、最終面接で重視されやすいのは次のようなポイントです。
・自社の将来的な方針にマッチする人材か
・入社意欲が高く、長期的な活躍が見込めるか
・自社の企業風土に問題なく馴染めそうか
実際の業務上で必要とされる、実践的な能力や実績などは、一次面接や二次面接でチェックされやすい部分です。最終面接では、事業運営や経営の観点から、自社の今後を担う一員として相応しいのか判断が下されます。組織や業績にどのような影響を与える人材なのか、おもに企業として目指す方向性に対して、どう適合するのか確かめる段階となるのが最終面接です。
最終面接までに準備しておきたい対策

では前述にもあるような、最終面接で重視されやすいポイントも踏まえて、あらかじめ準備しておきたい対策方法も見ていきましょう。
今までの面接で回答してきた内容の整理
例えば志望動機や自己PRなど、前回までの面接における評価を再確認する目的で、今までと似たような質問がされるケースも多くあります。また入社する意思の一貫性を確かめる意味でも、履歴書や職務経歴書などで示した内容をあらためて聞かれる場合も。そこで内容にブレがあると、「自社でなくてもよいのでは」など、信頼性に欠けてしまう可能性もあります。最終面接前には、これまでに示してきた志望動機や自己PRなど、今一度振り返って整理しておくことも重要です。同時に、さらに深掘りした自己分析をしておくと、志望先の企業で働きたい根拠がより明確になり、説得力の高い内容につながっていきます。
より徹底した業界・企業研究で志望先に対する理解度を深める
先ほども出てきたように、最終面接では、自社の今後を任せられる人物なのか見極めていきます。ミスマッチによる早期離職を防止する意味でも、企業側としては、できるだけ自社に対する理解度の高い人材を採用したいのが本音です。そこで最終面接では、入社意欲の高さや希望するキャリアパスなど、志望先の事業と関連させながらアピールすることが不可欠。それが志望先の経営方針や戦略にマッチしているほど、採用に値する人材としての高い評価に直結します。そのためにも最終面接前には、今まで以上に徹底した業界・企業研究をしておくことも重要です。志望先の業界や企業に対する理解度が深めることで、自分自身の理想の働き方と、どう適合しているのか確かな裏付けを示しやすくなります。
入社後からの中長期的なキャリアビジョンや目標を設定しておく
志望先の企業で実現したい将来像を明確に示すことで、経営面や事業成長に対する、戦力としての先を見据えた貢献性が伝わりやすくなります。企業側としても、確かなキャリアビジョンや目標を持っている人材であれば、長い目で見たポテンシャルに期待できます。また入社後のキャリアビジョンや目標など、志望先の企業の方向性に深く関連させることで、その会社でなければならない根拠にもできるでしょう。最終面接に臨む前には、しっかりと入社後のイメージを固めておき、自分がどのように活躍できるのか示すことも内定につなげるためのコツです。
最終面接で聞かれやすい質問10選

ではここからは、実際に最終面接で聞かれやすい、よくある質問の一例をご紹介していきます。
自己紹介・志望動機・自己PRをお願いします
前述でも触れているように、ここまでの面接の再確認として、今までにも回答してきた内容と似たような意図の質問がされることも多くあります。基本的には今までの内容と同じ方向性で問題ありませんが、より精度の高い回答にできるとベストでしょう。
(例)自己PR
私の強みは、新規開拓の営業活動の経験をもとに、今までにはない販路を見つけ出すノウハウを培ってきた点です。前職では○○の商材を取り扱うなかで、SNSや一般アンケートをもとに、ニッチな顧客ニーズを見つけ出すことで売上アップにつなげてきました。実際にこうした徹底した市場調査から、毎月平均○~○件の顧客獲得に成功してきた実績があります。このノウハウを活かし、御社の△△の事業拡大にも貢献していきたい所存です。
他社ではなく弊社を選んだ理由は何ですか?
自社に対する理解度を見極めてミスマッチを防ぐ意味でも、上記のように志望動機から一歩踏み込んだ質問がされるケースも少なくありません。企業側としても、どうしても自社でなければならない根拠が見えてこなければ、なかなか採用を決めるのは厳しいのが事実。仮に同業他社で似たような会社があれば、何かしらのキッカケで、そちらの企業に人材が流れてしまうリスクがあります。もちろん他社を否定するのはNGですが、なぜ志望先の企業に入社したいのか、その会社ならではの独自の優位性を示すようにしましょう。
(例)
御社が手がける○○の商品は、企業理念でもある「~~」との想いを込めて提供されており、実際にお客様からは「△△」といった好評の声が挙がっています。その背景にあるのは、「~~」の企業理念にもとづく商品開発と、□□によるお客様との信頼関係だと感じています。そこで私の強みでもある市場開拓のノウハウも活かしつつ、もっと◇◇のようなお客様にも、御社の商品がお届けできるのではないかと存じます。御社だからこそ、私の理想とする△△な商品提供や、強みを活かした事業貢献ができるのではないかと考えて志望しました。
弊社に入社して何を実現したいですか?(事業をどう成長させたいか?)
入社後にどう活躍してくれる人材なのか、ポテンシャルを見極める目的で、上記のような質問がされることもあります。どのように組織や事業の成長に貢献できるのか、自分なりの考えで構わないので、例えば「こんなことに挑戦して利益を出したい」などのビジョンを明確に伝えるのがベストです。
(例)
御社の○○の商品は、現在は△△の分野に特化していますが、入社後には新しく□□や◇◇などの市場にも進出できるのではと考えています。私がこれまでに培ってきた販路を広げるノウハウをもとに、新たに~~を試みることで、□□や◇◇などの顧客獲得に貢献するのが一つの目標です。
弊社ではどのようなキャリアを叶えたいですか?(入社後の将来像は?)
ここまでにも出てきているように最終面接では、長期で戦力となって成長を遂げていく人材なのか、十分に見極めることも重視されます。そこで求職者側にも、志望先の企業で長年にわたって活躍するイメージがないと、今後を任せられる人物と判断するのは難しいでしょう。どのように力を発揮していきたいのか、志望先の企業での将来性も含めて、あらかじめ明確に示せるようにしましょう。
(例)
御社では、まずは○年目を目途に、△△を達成するのが目標です。そして△年目には□□にもチャレンジして、◇◇の部分から御社の事業拡大にも貢献し、新たな分野への進出の足がかりをつくっていきたいとも考えています。さらに◎年目には~~のポジションを目指し、▼▼にも取り組みながら、組織の成長を促すことにも尽力していきたい所存です。
今までにもっとも苦労した経験はありますか?
将来にわたって自社の事業を担う一員として、存分に力を発揮できる人材なのか見極めるには、失敗を乗り越えた経験をしているかどうかも重要。どのような仕事でも、想定しない事態は起こり得るからこそ、失敗から学んだり改善したりする行動力も大切です。単純に「こんなトラブルで大変だった」というだけではなく、そこから何をしたのか、失敗からチャンスに変えられる力をアピールしましょう。
(例)
前職の営業時に、スケジュールの確認漏れから、長年のお付き合いとなる得意先への納品が遅れそうになるミスをした経験があります。発注ミスが発覚した際に、○○や△△の対応により発送方法を調整し、□□になるように手配をおこないました。結果的にトラブルは防いだものの、◇◇円ほどの赤字となり、~~や~~などの回収対策に取り組みました。この経験から以降は◎◎のツールを導入し、他の社員にも共有して社内でのトラブル防止策を試み、実際に納品ミスは◆◆%まで減少しています。また▼▼だけでなく、■■の重要性も一層認識し、その後は○○も心がけるようにしています。
あなたが仕事をするうえで大切にしていることは何ですか?(やりがいなど)
自社にマッチした人物なのか判断するうえで、仕事に対する価値観やスタンスなどが社風に合っていることも大切な要素になります。上記のような質問では、人柄や働くモチベーションなどをチェックして、企業風土との相性を見極める場合が多く見られます。例えば自分にとってのやりがいやポリシーなど、率直な考えを示すことを意識してみるとよいでしょう。面接だからといって取り繕うと、何かしら違和感が出てしまうケースは珍しくありません。具体的な体験談を交えながら、自分の素直な言葉で伝えてみましょう。
(例)
私が大切にしているのは、些細なことでも、積極的に自分なりのアイデアを形にすることです。普段からの習慣として、何か思い浮かんだ時には、必ずその場でメモをするようにしています。そして機会があれば実行に移すことで、トライアンドエラーで次のアイデアにつながり、どんどん新しい発想が出てくることに楽しさを感じています。また日常的に新たな試みを思い浮かべることで、例えば営業時のお客様への提案で使えたり、商品の販売企画に展開できたりなどの成果にもつながっています。実際に(エピソード)といったこともあり、お客様にも喜んでいただけた時には、大きな達成感も得られました。
最近で印象に残っているニュースはありますか?
事業の成長や業績拡大を目指すには、社会全体の動向に対する認識を持っておくことも欠かせません。こうした時事的な問題意識や、自分なりの考えを示すことで、きちんと社会情勢への関心のある人材との評価につながります。できれば志望先の企業や業界が関連する話題だと、時事問題をビジネスに活かせる人材として印象に残りやすいでしょう。
(例)
近年では○○の最新技術が広まってきているなかで、社の△△の商品でも、そのテクノロジーを活用した開発に取り組む方針だとホームページで拝見しました。○○のテクノロジーは~~などの効果や性能があり、御社の商品では□□のように展開できるのではないかと考えています。入社後には、自分なりにも○○のテクノロジーの研究をおこない、御社の新たな分野への進出に貢献していきたい所存です。
弊社の社内を見てどう思いますか?(社風や雰囲気)
上記のような質問では、自社の企業風土との相性を確かめると同時に、入社したい意欲の高さを見極めている場合が多く見られます。単純に求人情報やホームページ・採用サイトを見た内容ではなく、今までの面接で来社した時にどう思ったのか、自ら体感した印象を振り返って伝えられると自然な感想になります。
(例)
以前に面接でお伺いした際、フロア内のミーティングスペースで集まっているグループがいくつかあり、賑やかな雰囲気でコミュニケーションが盛んな点が印象に残りました。私自身も、仲間と積極的に連携しながら業務を進める姿勢を大切にしているので、御社のような社風ならすぐに溶け込めそうだと感じています。
転職状況はどうですか?(志望先が第一志望か)
入社意欲の度合いを見極める意味で、上記のような質問をされるケースが見られるため、もし第一志望なのであればその旨を率直に伝えるようにします。ただし複数社の選考に進んでいて、まだ迷う余地がありそうなら、なるべく誠実に事実を示すのが無難です。もちろん第一志望として前向きに検討しているのを前提に、現状の説明をするようにしましょう。
(例)
現在は御社の他に、同業の1社と○○業界の企業1社で選考に進んでいる状況です。2社ともに○月○日頃には選考結果が出る予定です。現状としては検討中ですが、御社の△△の部分に強い魅力を感じており、第一志望の一社として考えております。御社に入社できた時には、□□のように活躍して貢献したい所存です。
何か質問はありますか?
こちらも自社に対してどれほどの関心や興味があり、入社したい意識があるのか確かめる要素として、質問されるケースが多く見られます。こうした逆質問は、いくつか用意しておくと、入社意識の高さもアピールしやすいでしょう。最終面接の逆質問については、実際に活用できる例文も含めて、以下から詳しくご紹介していきます。
最終面接の逆質問に活用しやすいサンプルリスト

最終面接の逆質問では、経営方針や戦略をはじめ、求人情報や企業ホームページ・採用サイトからは判断できない内容を聞いてみるのがベストです。例えばホームページを見ればわかるような内容では、調査不足と評価されてしまう可能性も。また待遇や福利厚生などの労働体制も、「条件だけで職場を選んでいるのでは?」と不信感を抱かれてしまう恐れがあるため避けるようにしましょう。なお最終面接の逆質問のサンプルとして、次のような例が挙げられます。
・御社で活躍されているのはどのような方ですか?どういった傾向の方が特に成果を出されていますか?
・○○の事業拡大に向けてまずはどのような戦略を検討されていますか?
・御社の△△の社風に共感しておりますが、こうした企業風土はどのようにして生まれましたか?
・御社で働くなかで、どのような考え方や姿勢を一番重視してほしいとお考えですか?
・御社の仕事としてもっともやりがいや面白さを感じられるのは、どのような時ですか?
まとめ
新たな人材を受け入れることは、企業側としても経営面に大きく影響する要素であり、最終的な採用の判断をおこなうには十分な検討が不可欠です。そのため最終面接では、いかにして自社の事業に力を添えてくれる人材なのか、しっかりと見極めるための質問が中心となります。また人材側からの逆質問も、採用の可否を決めるのに重要な部分で、「特にありません」など関心のない姿勢を見せてしまうのはNG。企業側からの質問も自分からの逆質問も、「ここで自分の実力を発揮したい」との熱意が伝わるように心がけるのがベストです。最終面接の際には、ぜひ本記事も参考に、内定につなげるための準備と心がまえをしていきましょう。
