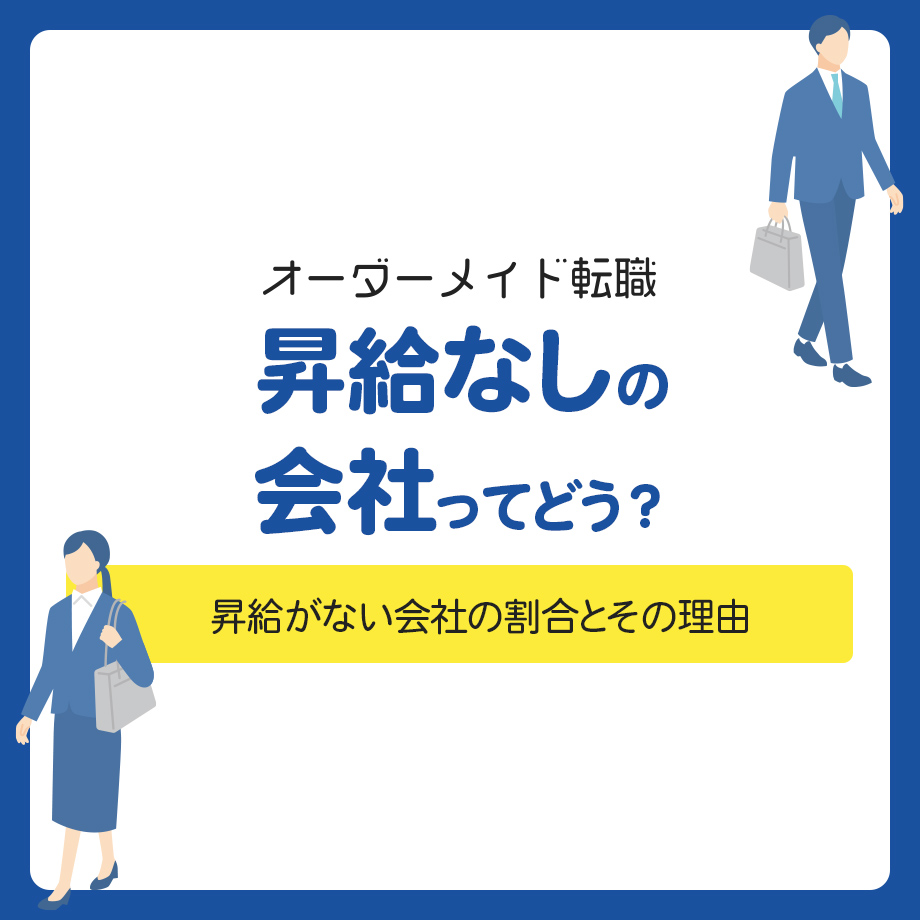
「昇給なし」と聞くと、あまり待遇のいい印象につながりにくいかもしれませんが、一概にそうとは言い切れません。仮に正式な昇給制度はないにしても、その他に好条件で働きやすい仕組みがあるなど、会社によって給与をはじめとした待遇の内容は大きく異なります。とはいえ状況次第では昇給制度がないことで生じるデメリットもあり、もし現職において給与面で悩んでいるなら、転職を考えたほうがいい可能性もあります。そこで今回は、昇給なしの会社がどれくらい存在するのか具体的なデータをはじめ、実際に働くうえで確認しておきたいポイントや注意点などを解説します。
昇給制度のない会社は全体の1.5~2割前後
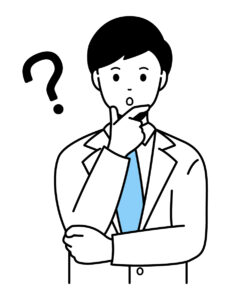
厚生労働省の調査(※1)によると、毎年決まった基準で基本給を上げていくような、正式な定期昇給制度がない企業の割合は12.7%(一般職対象)。管理職に対する定期昇給をしていない企業の比率は、17.2%とのデータが出ています。さらに令和6年度においては、「制度はあるものの実施しなかった、または延期した」と回答した企業が2.9%で、一般職に対する昇給をしなかった会社は合計15.6%との結果になりました。また対管理職になると、「制度はあるものの実施しなかった、または延期した」と回答した企業は4.7%で、令和6年度では全体の21.9%が昇給していない状況にあります。
こうしたデータにもあるように、そもそも昇給制度がない企業も一定数は存在しているのが現状です。ちなみに昇給制度の有無は、各企業の判断で設定できる待遇で、実際に導入していなくても違法ではありません。ただし就業規則や労働条件通知書などに、「昇給あり」との明記があるにも関わらず、賃金が上がらないのは契約違反に当たります。とはいえ「本人や会社の業績による」などの特記事項がある際には、場合によっては昇給しないケースもあります。
(※1)厚生労働省「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」
「昇給なし」の会社で考えられるパターン例

会社にもよりますが、さまざまな背景から、あえて「昇給なし」としている場合も多くあります。昇給しない理由としては、例えば「人件費削減のため」など、マイナスなものばかりではありません。では実際に、昇給のない会社で考えられる例として、具体的にどのようなケースがあるのか見ていきましょう。
基本給を高めに設定している
そもそもベースとなる基本給の水準を高くして、従業員の収入面の安定性を確保している会社もなかにはあります。例えば昇給はあるものの年功序列の制度では、特に年齢が若いうちは、基本給が低めに設定されていることも多くあります。そうなると入社後の初期段階では、なかなか十分な収入は得づらいケースも。そこで初任給から高めにして、その後は定期的ではなく、個人の業績などに応じて随時昇給するパターンもあります。この場合は昇給時期が明確ではないものの、各従業員の結果次第では給与が上がるチャンスも考えられます。
個人の成果や能力を給与に反映させている
例えば基本給に加えて、個人の成果にともなうインセンティブを支給する代わりに、昇給制度は設けていない会社もあります。こうした企業では、実力次第で収入アップを目指しやすく、自分の力でどんどん給与を上げやすいのがメリットです。もしくは能力給として、職務に応じた手当を付けることで、各従業員のスキルや業績に合わせて給与が上がる仕組みにしているケースもあります。いずれにしても、必ず昇給する保証はないものの、自分の出した結果がそのまま給与に反映されやすいのは利点でしょう。
独自の評価基準によって給与額を決めている
定期昇給として毎年必ず給与が上がるわけではないものの、従業員ごとの評価にともなって、基本給をアップさせている会社も少なくありません。社内で独自に設定した、一定の評価基準をクリアすると給与が上がる仕組みになっていて、その年ごとの結果に応じて不定期に昇給するようなイメージです。場合によっては「なかなか昇給しない」と感じているだけで、実際には決まった給与テーブルがあり、それに沿った勤務態度や業績などによって基本給が上がるケースもあります。
賞与や手当などの福利厚生を手厚く整えている
毎年の定期昇給がない分、例えば個人の業績などに応じて、賞与の金額を大きく変動させているケースもあります。社歴や年齢に関係なく、確かな成果を出すことで賞与額が大幅にアップにするなど、年収ベースで給与に反映しているパターンも見られます。もしくはスキル・資格などに応じた特別加算や、住宅補助・家族手当といった福利厚生で、昇給しない分をカバーしている場合も。基本給としてではなく、福利厚生によって給与が上がるような仕組みにしている会社もあります。
会社の業績に応じて変動させている
大前提として、企業全体としての十分な利益が出ていなければ、従業員にも反映できません。そこで毎年の定期昇給ではなく、会社の業績に合わせて、従業員全体の給与のベースアップをしているケースも見られます。年ごとの状況次第で昇給するかどうか変わってくるため、不定期になりやすい分、なかなか昇給しないと感じてしまう場合も考えられます。
昇給がない場合に想定されるリスク

給与は生活基盤を支える大切な要素であり、なかなか昇給が見込めないことは、大きなデメリットにつながるケースも少なからずあります。では昇給がないまま勤続していると、実際の働き方にどう影響する可能性があるのか、以下から詳しく見ていきます。
仕事のモチベーションを維持しづらい
例えば成果・能力に応じたインセンティブや手当などもなく、どれだけ結果を出しても給与が上がる見込みがないと、どうしても仕事のモチベーションは下がってしまいます。自分の努力が目に見えて評価されたり、何かしらの利益につながったりしなければ、どんどん働く意欲がなくなってしまうのは当然のことです。頑張っても収入に反映されないと、「結局やっても意味がない」と感じてしまい、そもそも仕事の手を進める気力自体がなくなってしまう可能性もあります。
スキルアップやキャリアにつながりにくくなる
もし昇給の基準が明確になっていれば、それを目標にして前向きに努力できますが、収入アップに期待できないとなかなか向上心が湧かないことも。結局のところ給与に直結しないことを考えると、自分のスキルを磨こうとする意欲も湧きにくくなってしまいます。また収入が少ないと自己投資などもしづらく、資格取得などのスキルアップを目指すのが難しくなりやすい一面も。また仕事のモチベーションが上がらなければ、成果を出す意欲にもつながりづらく、幅広い経験をして確かなキャリアを積むチャンスを逃してしまうリスクも考えられます。
精神的な負担がかかりやすくなる
なかなか収入が上がらないと、将来の経済面で不安を感じたり、給与が原因で意欲が湧かないことがプレッシャーになったりする場合も。昇給が見込めないことで、大きなストレスになってしまう可能性も考えられます。さらにストレスを抱えたまま無理に働くことで、余計に精神的な負担が大きくなってしまい、心身に不調をきたしてしまうリスクも。あまりに正当性がないまま昇給がなく、なおかつ収入的にも不安定なケースでは、転職を検討してみるのもいい方法です。
「昇給なし」が退職理由になりそうな時に見直したいポイント

仮に昇給しないのが原因で、退職を考えてしまう時には、慌てて動き出そうとするのは避けたほうが無難。まずは転職などを考える前に、以下のようなポイントを見直してみるのがおすすめです。結局のところ転職しても解決できない可能性もありますし、場合によっては「前の会社のほうがよかった」などと後悔してしまう可能性も。もし昇給しない部分のみが難点で、他の労働環境などで悩んでいることがないのであれば、焦って辞めるのではなく一度ゆっくり検討してみましょう。
そもそもなぜ昇給しないのか原因を探ってみる
場合によっては、ただ自分自身で認識していないだけで、何かしら昇給できる仕組みがあるケースも少なくありません。まずは昇給に関する制度がないか、例えば就業規則を見直してみたり、上司や人事担当などに確認してみたりするのがおすすめです。もしくは昇給できない原因は何なのか、機会があれば上司や人事担当などに聞いて調べてみる方法もあります。自分自身のスキル不足や会社の状況など、何かしら原因がわかれば、収入アップに向けて何をすべきか具体的な対処法も見えやすくなります。
上司に相談してみる
前述のように個人の能力や成果によって昇給できるケースなら、今後どうしたら給与アップにつながるのか、直接相談してみるのもいい方法です。例えば、「契約数○件を目指す」「□□の業務に対応できるようにする」など。どうすれば昇給できるのか、具体的な行動指針を教えてもらえる可能性もあります。また新たな資格の取得やスキルアップによって、特別な手当が支給されるようになって昇給できることも。もし自分自身に原因がありそうなら、昇給に向けて目指すべき方向性など、一度相談してみるのもよいでしょう。
現職以外で収入を増やす方法を考える
もし副業が認められているなら、手の空きそうな時間を使って、現職以外のルートから収入を確保するのもいいかもしれません。例えば現職とは少し異なる副業に挑戦してみることで、新たなスキル習得につながる可能性もあります。なかでも、Webライティング(記事作成)・Webデザイン・プログラミングなどは、在宅でもはじめやすく副業でよく見られる代表例です。場合によっては、今までになかった新しい仕事のチャンスが生まれるかもしれませんし、自分で勉強してみて副業としてチャレンジするのもよいでしょう。もしくは株などの投資を勉強して、資産を増やす手段を検討してみるのも一つの方法です。
まとめ
昇給制度は、各企業の判断によって、どのように適用するか決められるものです。実際に昇給制度がない会社も一定数存在しており、どの企業でも設けられている待遇ではありません。とはいえ昇給制度がない分、別の手当や福利厚生などでカバーしているケースも。昇給にともなう仕組みは、企業ごとに大きく変わってくるので、もし給与面で不安があればまずは社内の規則や制度を十分に確認してみましょう。もちろん昇給がないからといって、待遇が充実していないとは限りません。しかしあまりに労働条件が厳しいなど、昇給以外の部分でも気になる悩みがあれば、一度転職も検討してみることをおすすめします。
