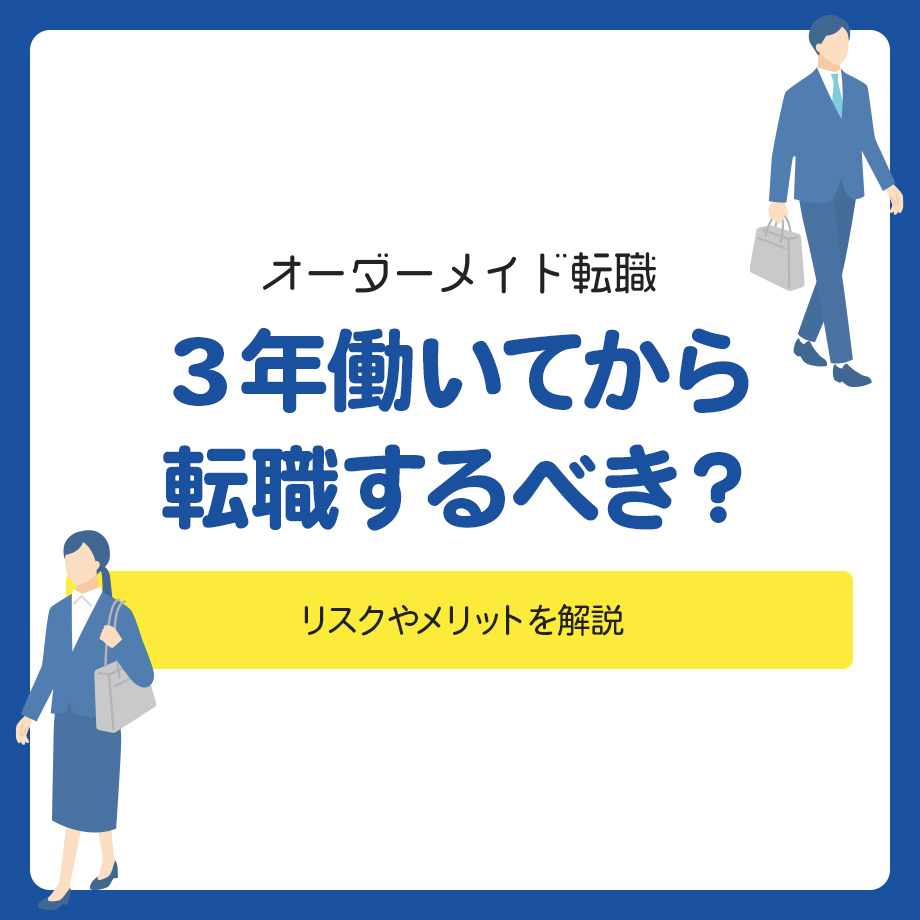
「今の職場のままでは先が見えない」「なんとなく不満が多くて仕事のやる気が起きない」など、現職での満足感や充実感があまり得られていない時には、いっそ転職すべきどうか悩むこともあるでしょう。そうした場合に、まだ入社してからの年数や職歴が浅いと、「このタイミングの転職は印象が悪く見えそう」などの不安を覚えるケースも珍しくありません。もちろん明確な意思があれば、基本的には、どのような時期に転職をするのも個人の自由です。しかし世間的には、「少なくとも3年は働くほうが無難」との考え方も見られるため、結局のところ転職までの期間に迷ってしまうのも不思議ではありません。では実際に入社期間の短い時に転職を検討する際に、とりあえず3年は続けたほうがいいのか、そのメリットやリスクも交えながら解説していきます。
そもそも「3年働いてから転職」といわれているのはなぜ?

基本的に「3年働いてから転職すべき」との概念には、はっきりとした根拠はなく、一般的なキャリアの基礎を構築できる目安の期間として広まっている考え方です。だいたい3年ほどかけて、担当業務に必要なスキルを習得しつつ、中堅層のリーダーポジションに向けたステップに進んでいくケースがよく見られます。このように、業務を遂行するうえでの基礎力+少しレベルアップした応用力が身につく期間を経ることで、より理想に近いキャリアパスを見極めやすくなると考えられています。当然ながら、転職に踏み切る時期は個人の自由ですし、ただ前職での社歴が短いからといって採用されないわけではありません。新規採用を考える企業側としては、あくまで入社後にどう活躍できそうなのか、各人材の今後に期待しています。もちろん今までの職歴も加味されますが、大切なのは、その企業に対して貢献できるスキルや能力があるかどうかです。たとえ前職での経験年数が浅くても、志望する企業が求める強みなどがあれば、採用につながる可能性は大いにあります。「入社から3年」は、一つの基準として、期間にとらわれすぎずに状況に応じて転職を考えるのがベストです。
新卒社会人の3割以上は入社3年以内に離職している
厚生労働省の調査(※1)によると、新卒から就職後3年以内の離職率として、大卒では31.2%、高卒では36.9%。新卒者の3割以上は、比較的短期間で離職しており、早い段階からの転職者も一定数存在することがわかっています。働き出してから3年以内の転職は、決して珍しいことではなく、どうしても無理に続けなければならないわけでもありません。自分自身の状況や希望によって、転職の時期は十分に検討してみましょう。
早くから転職を決める前に3年勤続するメリット

では一般的な離職時期の目安とされている、「とりあえず3年働く」メリットとして、転職などにどのような影響があるのか具体的に見ていきましょう。
「すぐに辞めてしまう」懸念を軽減できる
少なくとも3年は続けていれば、次の転職先となる企業側からも、「一通りの経験をしたうえでの新しい選択」と捉えてもらいやすいメリットがあります。勤続3年は経っていると、例えば後輩の指導やチームのリーダーなど、重要度や難易度の比較的高い役割も経験しているケースが多いでしょう。ある程度の業務幅を体感していることで、今後のキャリアや将来像に向けた転職であることを提示しやすく、企業側からも前向きなステップとして見てもらいやすい一面があります。例えば不満の蓄積などによる、突発的な転職ではないことが伝わることで、早期離職の懸念が軽減されて採用につながりやすくなる効果が見込めます。
十分な退職金や賞与に期待できる
退職金や賞与は、勤続年数に応じて支給金額が上がりやすい傾向にあります。そのため3年程度は続けたほうが、ある程度の退職金や賞与を受け取りやすい見込みがあり、金銭的なメリットにも期待しやすい一面も。特に退職金は適用条件として「勤続3年以上」の社内規定を設けている企業も多く、福利厚生としての制度自体は存在しても、あまりに社歴が短いと支給されないケースも見られます。こうした現職における待遇面も考慮するなら、少なくとも3年は続けていたほうが恩恵を受けやすい部分もあります。
経験を積み重ねるなかで新たな気付きが得られることも
3年続けていくことで、自分なりに可能性を見出せたり、活躍の場が広がってやりがいが出てきたりするケースもあります。わざわざ転職しなくても、今の仕事のまま、理想のキャリアパスを実現できるイメージが湧いてくることも考えられるでしょう。いざ転職するとしても、希望の会社になかなか採用されなかったり、新しい職場との相性が合わなかったりするリスクも想定されます。例えば担当業務に対して、多少の不満や苦手意識などがあっても根気よく続けてみることで、転職せずに解決できる手段を取れる場合も。「業務内容に少し不服があるけれど人間関係はいい」「待遇や労働条件には満足している」など、少しでも続けられそうな検討の余地があるなら、焦って転職しないのも一つの方法です。
転職までの目標期間を設けることで冷静な判断ができる
「とりあえず3年は続けてみよう」という目標があれば、一時的な衝動や感情による突発的な行動を防ぎやすくなります。大きなストレスや不満に見舞われることがあっても、「3年は続ける」との目標を思い浮かべることで、気持ちが落ち着くことも。こうして冷静に自分を見つめ直しながら、長い期間をかけて十分に自己内省・分析ができるため、より的確な判断もしやすくなります。転職すべきかどうかの見極めるために、あえて3年を目安として、猶予期間を設けておくのもいい方法でしょう。
転職までにとりあえず3年続ける場合に注意しておきたいリスク

転職したい気持ちはあるものの、一般的な認識として「何年かは続けたほうがよさそう」など、漠然としたイメージのみで3年勤続するケースでは特に注意が必要。転職の先延ばしにより、次のようなリスクが考えられることも頭に入れておきましょう。
漫然とした気持ちが大きいと時間の浪費につながりやすい
ダラダラと惰性で続けてしまうと、なんとなく仕事はこなしていても、前向きな意欲や向上心がないまま働くことになります。さまざまな業務を経験しても、新たなスキルを得ようとしたり学んだりする姿勢が生まれにくく、場合によっては時間のムダになってしまうケースも。もし本当にやりたい仕事があるなら、早くから挑戦したほうが、時間を浪費せずに必要なノウハウを磨くことができます。すでに進みたい方向性が決まっているなら、経験年数にとらわれすぎずに、早期から転職を決めたほうがいい可能性もあります。
離職のタイミングを逃して辞める負担が大きくなることも
何かしら不満はあるものの、とりあえず続けていくなかで、規模の大きいプロジェクトや責任のあるポジションなどの担当になる可能性も考えられます。そうなると本人としても任された義務感や使命感から、辞めたくても辞める心理的負担のほうが大きくなってしまい、転職に踏み切れない事態につながることも。さらに会社としても、長く続けた人材の離職にともなう欠員補充の労力や難易度から、引き止めたい動きが見られることもあります。決断を先延ばしにする分、自分自身の気持ちとしてもどんどん転職しづらくなってしまい、理想のキャリアビジョンが実現しにくくなるリスクもあるでしょう。
新卒入社の場合にはポテンシャル採用枠で不利になる可能性も
一般的に新卒からの社会人3年未満であれば、若手採用で有利になりやすい、第二新卒枠に該当します。まだ経験が浅い分、先入観や固定観念が薄く、育成を前提としたポテンシャル採用に期待しやすいのが第二新卒です。「とりあえず3年」と考えながらも、惰性で4年や5年と長く続けてしまうと、第二新卒としての採用枠から外れてしまいます。特に「現職とはまったく異なる職種や業種にチャレンジしたい」など、未経験からの挑戦を考えるなら、できるだけ第二新卒枠に入る段階で転職するのがおすすめです。
過度なストレス感から心身状態を悪化させてしまう
あまりに過酷な労働条件や、パワハラ・セクハラなどのコンプライアンスに反した職場環境などの場合には、無理して続けるのは避けたほうが無難です。過度なストレスを溜め込んでしまうと、場合によっては日常生活に支障をきたすような、心身症状や精神疾患につながってしまう危険性もあります。すでに大きな負担や疲弊感を覚えていたり、出社するのが苦痛に感じたりするほどの状態であれば、なるべく早めに転職を検討してみることをおすすめします。
入社3年以内で転職を決める際に意識したいポイント
では実際に、入社から3年以内の短期間で転職する場合に、気を付けておきたいポイントもご紹介していきます。
マイナスに見えない転職理由や志望動機を考えておく
「入社3年以内」は職歴として短い分、採用選考時には転職理由や志望動機が重視されやすい傾向にあります。転職を決めた根拠があいまいだったり、ネガティブな姿勢が見えたりすると、「せっかく入社しても続かないのでは」「もっと好条件の他社でもよさそう」など、企業側のさまざまな懸念が生まれやすい部分も。書類選考や面接に向けては、なるべく前向きな転職理由や志望動機を考えておくのがベストです。例えば挑戦してみたいことや実現させたいビジョンなど、これから“やってみたい”意欲を軸として、転職理由や志望動機の方向性を固めていくとマイナスな印象を避けられます。
転職以外に現状を変える方法はないか十分に検討する
部署異動や転勤など、今までと同じ社内いながら環境を変えて、不満や問題を解消する方法もありま現状における不満や問題は、転職したからといって必ず解決されるとは限りません。場合によっては、現職よりも状況が悪化したり、なかなか希望の転職先とのマッチングができなかったりするリスクもあります。早まって離職してしまう前に、今と同じ職場で現状から改善できないか、一度振り返って考え直してみることをおすすめします。
できるだけ長期的なキャリアプランを見据えて転職先を探す
入社3年に満たないような、勤続年数が浅いうちの転職は、必ずしも不利になるわけではありません。とはいえ短期間の職歴が多すぎるのも、「少しでも不満があるとすぐに辞めてしまうのでは」など、企業側としては早期離職の懸念が湧きやすくなる一面があります。短期間の職歴をムダに増やさないためにも、転職を考える際には、何年か先まで想定した長期的なキャリアプランをイメージしながら志望先を探すことも大切。自分がどのような姿になりたいのか、理想的な将来像をしっかりと思い浮かべながら転職先を検討してみましょう。
まとめ
転職のタイミングに向けて、とりあえず3年働くべきなのか、人それぞれの状況次第で大きく異なります。今回見てきたように、3年勤続してからの転職にはメリットもリスクもあり、転職までに適した期間とは一概にはいえません。自分にとってベストな時期に転職するには、まずは今後どのようなキャリアを歩んでいきたいのか、しっかりと見極めておくことが重要です。ぜひ本記事も参考に、より最適な転職時期を検討してみてください。
