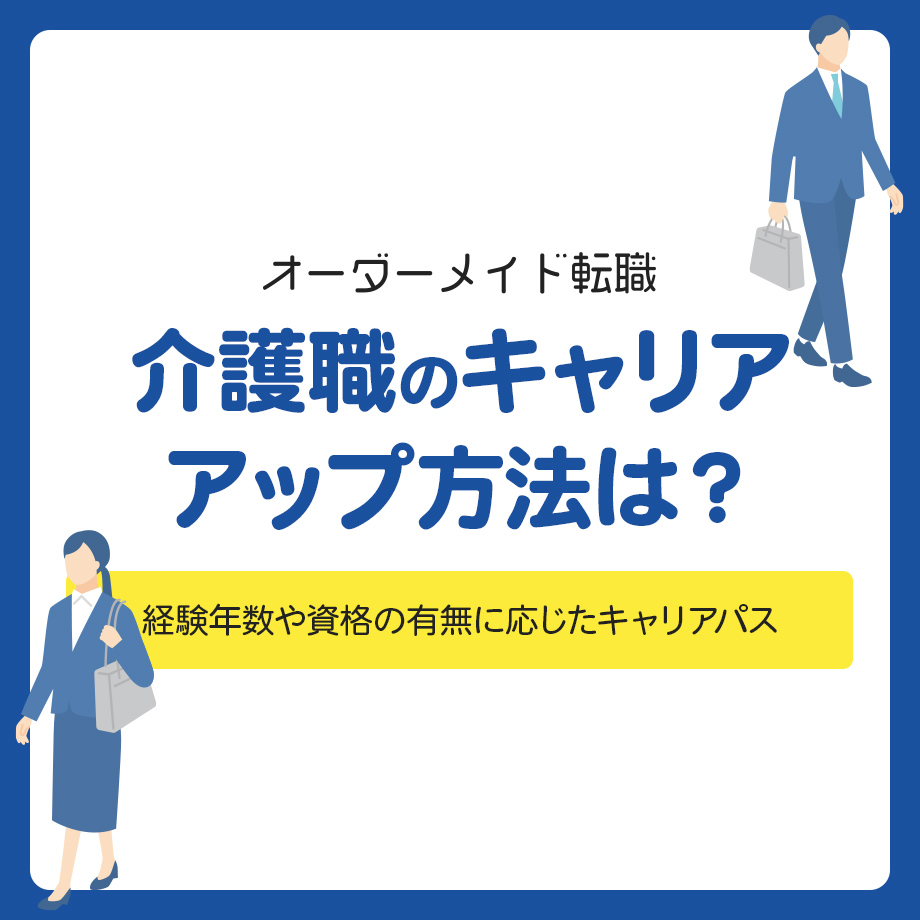
少子高齢化が進む昨今、介護職の需要は年々増加しており、なおかつ専門性の高い業界として安定したキャリアを積める仕事でもあります。また社会貢献度の高さや、ご高齢者の安心の毎日を支えられる確かな充実感などもあり、この先も長く続けていきたいと感じることは多々あるでしょう。そこで今回は、介護職におけるキャリアパスとして、経験年数や必要な資格に応じて選べるルートを解説。介護職として、将来を見据えながらキャリアアップしていく方法をご紹介します。
介護職は無資格からスタート可能

介護職は、福祉に関わる専門的な仕事ではありますが、特別な資格がなくても就職はできます。特に介護業界は、慢性的な人手不足もあり、無資格・未経験から採用しているケースも多々見られます。
ただし2024年からは、資格のない介護人材を対象に、認知症のケアに対応していくための「認知症介護基礎研修」の受講が義務化されました(入職後1年の猶予期間あり)。そのため厳密には、完全な無資格で介護職に就くことはできませんが、勤務先によっては入職してから「認知症介護基礎研修」を受講できるパターンもあります。この際には、入職時点ではまったく何の資格がなくても、介護職に就くことは可能です。
もし仮に現時点で無資格のまま介護職に就いている場合、勤務先より「認知症介護基礎研修」の受講を求められる可能性が考えられます。もしくは「認知症介護基礎研修」の受講が免除される、他の専門資格の取得を推薦されることも想定されるでしょう。
介護職のキャリアアップにつながる資格は?
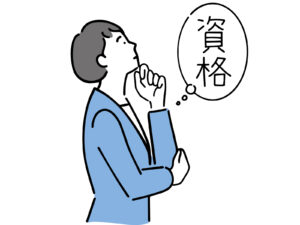
基本的に介護職を続けていくためには、「認知症介護基礎研修」修了者が前提となりますが、その他にも今後のキャリアにつながる資格がいくつもあります。この先も、介護職として給与アップや管理職などを目指していきたい場合には、次のような資格の取得を目指していくのがおすすめです。
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修
「介護初任者研修」と「介護福祉士実務者研修」は、いずれも介護職の入門とされる公的資格です。介護職の第一関門となるのが「介護初任者研修」で、その上位資格とされるのが「介護福祉士実務者研修」に当たります。
ちなみに「介護初任者研修」の資格がない介護職の場合、基本的には利用者様の身体に直接触れるケア(入浴・排せつ・体位変換などの身体介護)はできません。こうしたケアをおこなうには、介護施設内かつ有資格者による指導が必須とされており、単独では対応できないとされています(訪問による身体介護も不可)。そのため介護職では、対応できる業務範囲を制限されないために、まずは介護初任者研修」の資格を取るのが一般的です。
なおその上位資格となる「介護福祉士実務者研修」を取得できると、介護現場における一部の医療ケア(喀痰吸引・経管栄養)に対応でき、さらに業務範囲を広げられます。加えて、訪問介護事業所の管理業務(サービス提供責任者)に就くための要件にもなります。
「介護初任者研修」と「介護福祉士実務者研修」は、どちらも特別な受験要件はなく、所定のカリキュラムの修了によって取得できます。まだ入職したばかりのうちは、「介護初任者研修」から取得していくのが基本ですが、ある程度の経験があれば最初から「介護福祉士実務者研修」を取ることも可能です。
介護福祉士
介護福祉士は、介護現場のプロフェッショナルともいえる国家資格です。3年以上の実務経験+所定の各種資格の要件を満たすことで、受験できる資格でもあります(福祉系高校・大学または養成機関修了者を除く)。
介護福祉士は一定の実務経験が必須となるため、介護職に就いて何年か経った中堅職員向けの資格です。なお前述にも出てきた「介護福祉士実務者研修」は、介護福祉士の受験要件にもなるため、あらかじめ取得しておくとレベルアップしやすいでしょう。
ちなみに介護福祉士を取得していると、次にご紹介していく、介護支援専門員(ケアマネージャー)の受験要件にもなります。介護福祉士の資格を目指すことで、業界内のキャリアパスをさらに広げることが可能です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護サービスの利用計画を作成できる専門資格です。介護を必要とする方に対して、どのような介護サービスを受けるべきなのか、個々の状況に応じた具体的なケアプランを立てる職種でもあります。ケアマネージャーは、介護施設内をはじめ、在宅での介護をサポートする居宅介護支援事業所などでも活躍できます。なお資格取得に向けては、「介護福祉士としての実務経験5年以上」が必要(その他所定の資格も可)。介護福祉士からのステップアップにも適した資格です。
社会福祉士
社会福祉士は、介護を必要とする高齢者に限らず、生活に困っている方からの相談や問題解決に対応する専門資格です。心身に障がいを持つ方や経済的な困難を抱えている方などに対し、利用できる福祉サービスや支援制度の案内といった、必要なサポートを受けるための提案・連携などを担います。幅広い福祉の知識を持つエキスパートで、介護関連の資格ではトップクラスの位置付けとなります。さらに介護分野に限らず、福祉全般に携わることができ、より活躍の範囲を広げてキャリアアップしたい時におすすめ。なお社会福祉士を目指すには、一定以上の相談支援実務(介護支援専門員や生活相談員など)の経験が必要です。(※福祉大学・短大・養成機関修了者・福祉司等、これまでの経歴により異なる)
【経験年数別】介護職で目指せるキャリアパス

ではここまでに見てきた資格の取得時期も交えながら、具体的にはどのようなキャリアパスを目指せるのか、経験年数の目安も含めて解説していきます。
【経験年数3年未満】入門資格を取得してスキルアップ
まだ入職歴が浅いうちは、まずは実務経験年数などの受験要件がない、「介護初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」から目指してスキルアップしていくのが一般的です。もちろん必ず取得する必要はありませんが、現場を経験しながら資格を取っていくことで、より確かなノウハウとして定着します。また介護の現場では、「介護初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」の資格がないと対応できない業務もあるため、今後のスキルアップを考えるなら取得しておくのが無難。なかでも「介護福祉士実務者研修」は、介護福祉士やサービス提供責任者になるのに求められる資格でもあるので、取得しておくのがおすすめです。
【経験年数3年以上】リーダーや主任などの役職へ(介護福祉士)
実務経験3年以上になると、介護福祉士の資格取得を目指せるようになります。また介護福祉士の資格が取れると、現場のプロとして認定されることから、リーダーや主任などの役職に就けるチャンスも出てきます。その他にも、新人や後輩の教育・指導を担当したり、スタッフのシフト作成をしたりなど、介護福祉士の取得により責任のある管理業務を任されるケースもあります。
【経験年数5年以上】現場からのジョブチェンジ(介護支援専門員・社会福祉士)
経験年数5年を超えた先では、介護現場だけでなく、幅広いキャリアパスにチャレンジできる可能性が出てきます。例えば訪問介護事業所の管理業務を担うサービス提供責任者なら、「介護福祉士実務者研修」を取得していれば、経験年数に関係なくキャリアチェンジが可能です。
なお介護福祉士から実務経験5年以上になると、介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格取得を目指せるようになります。介護支援専門員(ケアマネージャー)として、各利用者様に最適な介護サービスを提供していくキャリアパスも考えられます。
また各介護施設では、利用者様の日常的な問題解決・メンタルケア・入退所の手続きなど、さまざまな相談援助を担当する生活相談員が配置されています。自治体ごとに定められた要件次第で異なりますが、十分な実務経験があれば、生活相談員として活躍できることも。利用者様にとっての頼れるアドバイザーとなる、生活相談員を目指すのも一つの方法です。なお生活相談員の要件としては、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事のいずれか、または介護福祉士か介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格があれば認められるケースが多く見られます。
【その後】施設長などの経営幹部へ
介護現場をはじめ、ケアマネージャーや生活相談員などの施設運営に関わる経験を積んだのちには、経営に携わる幹部層を目指すキャリアパスも考えられます。なお特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・グループホームでは、施設長や管理者の資格要件が設けられていますが、デイサービスや有料老人ホームでは特にありません。介護職としての確かなキャリアを積んだのちには、施設長などの経営幹部を目指せる可能性は大いにあります。もちろんいずれにしても、施設を経営していくためには、介護に関わる専門性の高いノウハウや経験は不可欠です。
まとめ
介護職は、社会福祉に関わる専門性の高い仕事で、さまざまな業務に必要とされる資格も数多く存在しています。こうした資格取得を目指していくことで、着実にキャリアアップができるチャンスも。また資格の取得や実務経験の積み重ねにより、介護現場だけでなく、適切なケアのプランニングや相談対応など幅広い形で利用者様のサポートができます。介護職では多彩なキャリアパスがあるため、ぜひ本記事も参考に、今後どのような道を目指すべきなのか検討してみてください。
