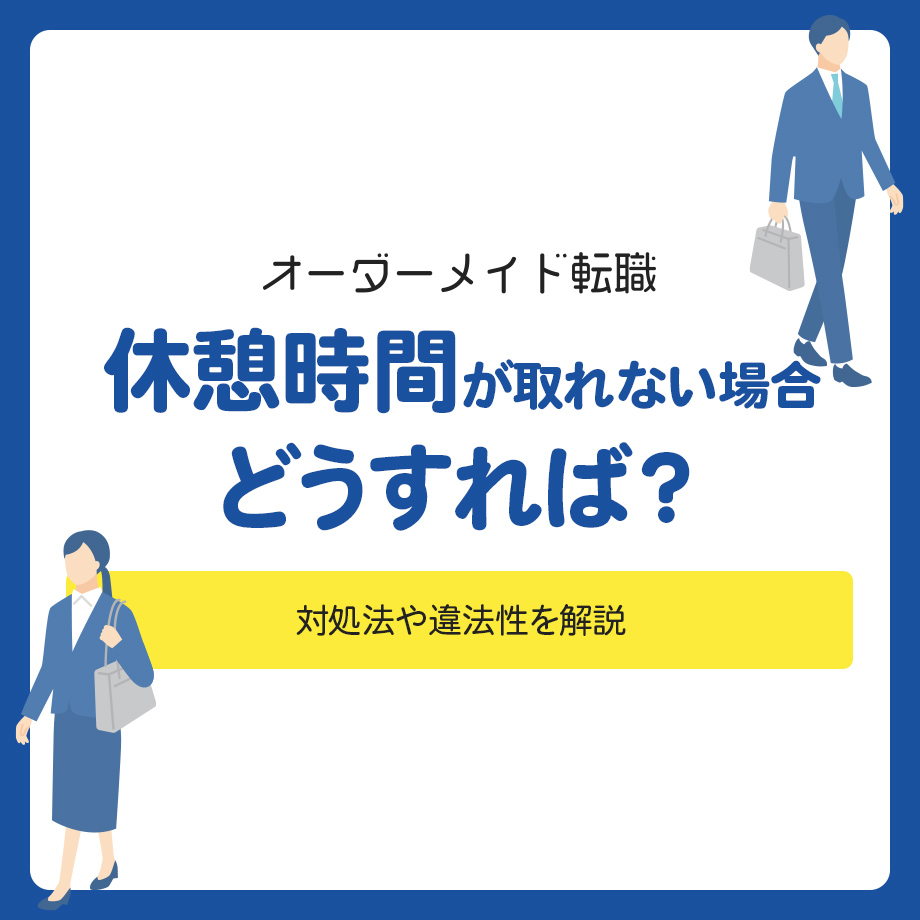
繁忙期や人材の欠員時など、なんとなく仕事が忙しくなってくると、勤務中の休憩の取り方があいまいになってくることもありがちです。また職場の状況次第では、「結局休めていない気がする」「きちんとした休憩時間が取りづらい」など、なかなか勤務中のリフレッシュができていないケースも見られます。そこで今回は、職場での休憩時間が取れない場合の対処法をご紹介。休憩時間の考え方や違法性など、労働問題の基礎知識も含めて解説していきます。
法律で決められている正しい休憩の取り方とは?

そもそも労働基準法では、一定の労働時間を超える場合、従業員には必ず法律にある規定以上の休憩を与えなければならないとされています。ちなみに労働基準法における休憩時間の規定は、1日6時間以上8時間未満の労働で45分以上、1日8時間以上の労働で1時間以上。こうした条件に該当する勤務形態にもかかわらず、休憩がない、もしくは規定に満たない休憩時間しかなければ違法となります。そのため次のような休憩の取り方ができていなければ、基本的には違法とみなされます。
勤務時間内のどこかで休憩を挟む
労働基準法の休憩時間は、あくまで従業員の疲労回復やリフレッシュを目的とするものです。仕事の最中に休憩時間を取って、きちんと心身を休められる体制にされているのが基本となります。始業・終業時間の前後に休憩を入れて、その他は連続した勤務にするのは違法に当たります。
仕事から離れて自由に過ごせる
労働基準法による休憩は、労働とは切り離して、従業員が自らの意思で時間を使えるものとしています。休憩時間内に戻れるのであれば、例えば「ランチに出かける」「ちょっとした買い物を済ませる」など、職場から離れて中抜けするのも問題はありません。反対に、「休憩中でも社内にいてほしい」など、休憩の過ごし方を制限されるのは違法となります。
【例外】休憩の取り方は従業員ごとに異なっていても可
労働基準法では、同事業所内の従業員には全員同じタイミングで休憩を与えなければならないルールもあります(一斉付与の原則)。ただし業務内容や人員体制などの状況次第で、一斉付与が難しければ、交替制などで個別に休憩を与えることも可能です(労使協定の締結による)。例えばシフト制での休憩でも、適切な時間が確保されていれば問題ありません。
【例外】従業員側の自己責任で休憩を取らないのは黙認
上長からの指導・監督があり、休憩時間の指示があるにもかかわらず、従業員自らの判断で労働を続ける際には特に法的な問題などは問われません。あくまで従業員の意思で休憩を返上している場合には、雇用者側にも違法性はなく、特別な罰則などもなく黙認されるのが基本となります。ただし雇用者側には、従業員の休憩時間を確保する義務があり、あまりに返上し続けると会社から好ましくないように感じられてしまう可能性があるため注意が必要です。
休憩時間の取り方で違法になるパターン例

ではここからは、休憩時間の取り方で注意したい、違法に当たるよくある事例も見ていきましょう。
来客や電話などの対応・作業発生時までの待機時間
休憩時間は、基本的には労働に拘束されずに、上長の命令・監督などに関係なく過ごすことができます。場合によっては、対応すべき作業などが発生するまでの待機時間が出てくることもありますが、これは労働基準法の休憩には該当しません。あくまで業務に対応する準備をしておくことになるため、手待ち時間として労働とみなされます。例えば「来客や電話があるかもしれないからデスクにいてほしい」など、待機のために休憩時間の過ごし方を制限してはならないとされています。たとえ実際には対応しなくても、会社からの指示で「休憩=待機」になっている時には違法となります。
「休憩なし」で勤務する代わりに遅出・早上がり
労働基準法の休憩時間は、必ず勤務中に確保しなければならないルールがあります。たとえ従業員側の意思で、「休憩を省く代わりに遅出・早上がりがしたい」との申し出をしても認められないのが原則。これを許可してしまうと、雇用者側の違法になってしまうため、きちんと勤務時間内に休憩を取れるように調整する必要があります。
休憩時間が細切れすぎる
休憩時間は、まとめて一括で確保しなくても、必要に応じて分割して付与してもよいとされています。仮に1日8時間労働なら、合計1時間以上の休憩があれば問題ないため、「30分+30分」「15分+45分」などの取り方もできます。ただし例えば「10分×6回」など、自由に過ごせる時間がほとんどないような休憩時間は、雇用者側の違法となる可能性も。あまり細切れに分割されていて、休憩した気にならないような場合には、違法とみなされることがあります。
残業して合計労働時間が6時間を超えたのに「休憩なし」
もし所定労働時間が「1日5時間」となっていて、6時間に満たない勤務形態なら、「休憩なし」でも問題はありません。また基本的には、残業そのものに対しては、休憩時間の付与義務もないのが原則。あくまで1日8時間以上の勤務に対しては、合計1時間以上の休憩があれば合法です。ただし残業が発生して、1日の労働時間が6時間を超過する際には、必ず一定の休憩時間を確保する必要があります。もしくは残業になって、1日の労働時間が6時間から8時間以上になった場合、合計して1時間以上の休憩を取れるようにしなければなりません。例えば所定労働時間が「1日6時間」で、残業により「1日8時間」になったにもかかわらず、休憩時間が「45分」のまま追加がなければ違法となります。
休憩時間が取れない・取らせてもらえない時にできる対処法

職場環境や業務の状況などによっては、十分な休憩がなかなか確保できないケースも珍しくありません。休憩が取れない原因次第でも異なりますが、勤務中の休息がなく作業効率やモチベーションなどが下がってしまうような場合には、次のような対策を検討してみましょう。
休憩が取れなかった時には別の方法で確保する
基本的に休憩時間は、賃金に置き換えることができない法律上の規定になっています。そのため「休憩が取れなかったから」といって、代わりにその分の賃金をもらうことはできないのが原則。もし休憩が取れなかった日があるなら、他のタイミングで再付与してもらうのが代案となります。または、まとまった休憩時間を取るのが難しそうであれば、分割して確保できるように調整する方法も考えられます。いずれにしても休憩時間が不足した分は、別の休憩時間で補てんする必要があります。
自分自身の業務の進め方に問題がないか振り返る
毎日の担当業務が追い付かず、常に休憩を省いた働き方になっている場合、自らの作業効率や仕事の進め方に課題が見つかる可能性も。まずは決まった勤務時間内で仕事が終わらない原因を探ってみることで、改善の糸口が見えてくることもあります。場合によっては自分自身ではなく、業務分担や人員体制などの職場環境に問題があるケースも考えられます。「なぜかいつも仕事に追われて休憩が取れない」と感じている際には、今までの1日のスケジュールなどを見直してみるとよいでしょう。
上司や人事・労務管理などの専門部署に相談する
例えば「人手不足で休憩を返上しないと回らない」「担当業務の性質上、休憩を取るのが難しい」などの場合、配属先における勤務体制を見直す必要があります。このような職場環境全体の改善が求められそうなケースでは、上司もしくは人事・労務管理などの専門部署に相談して、きちんと休憩が取れる働き方ができるように対策するのも一つの方法です。人員配置や業務の割り振りなどを変えることで、十分な休憩時間を確保できるようになる可能性もあります。
労働組合にかけ合ってもらう
労働組合は、待遇の改善など労働者を守るための活動をおこなう組織で、社内で設置されているのであれば休憩時間の相談もできます。労働組合の相談窓口に問い合わせをして、雇用者側にかけ合ってもらうことで、適切に休憩が取れるように対策を求める方法も考えられます。ちなみに社内に労働組合があるかどうかは、ハローワークの求人票を見るか、日本労働組合総連合会の「連合加盟労働組合リスト」から調べて確認することが可能です。
労働局や労働基準監督署の相談窓口に問い合わせる
労働局や労働基準監督署では、働くうえで発生するさまざまな問題に対応する、専門の相談窓口を設けています。もし「休憩を取らせてもらえない」など、企業側の管理体制に問題がありそうであれば、こうした行政機関の相談窓口に問い合わせる方法もあります。適切に休憩を与えないなど、実際に雇用者側に違法性が見られる際には、労働局長による助言・指導をしてもらうことが可能。場合によっては、紛争解決機関(弁護士など)へのあっせんを通じて対処してもらえることもあります。休憩時間の違法性が高いようであれば、労働局や労働基準監督署に相談してみるのもよいでしょう。
弁護士に相談する
休憩時間だけでなく、その他にも劣悪な待遇やパワハラなどのトラブルが発生している際には、弁護士に依頼して対処してもらう方法もあります。あまりに劣悪な職場環境が見られる際には、紛争解決の専門家でもある弁護士に相談して、どうすべきなのか判断してもらうのがベストです。
まとめ
休憩時間の確保は、雇用している企業側に課されている義務であり、適切に付与されないのは違法です。また休憩時間はあったとしても、しっかりと休めないような状態であれば、企業側の管理体制に問題があるといえます。ただし「仕事を中断しないほうが効率的」など、従業員自身の判断で休憩を取らずに業務を続けている場合、基本的に違法性はありません。このように休憩の取り方次第で違法性は異なるうえに、対処法も変わってきます。ぜひ本記事も参考に、まずは現状を把握しつつ、どのような対策ができそうか検討してみましょう。
