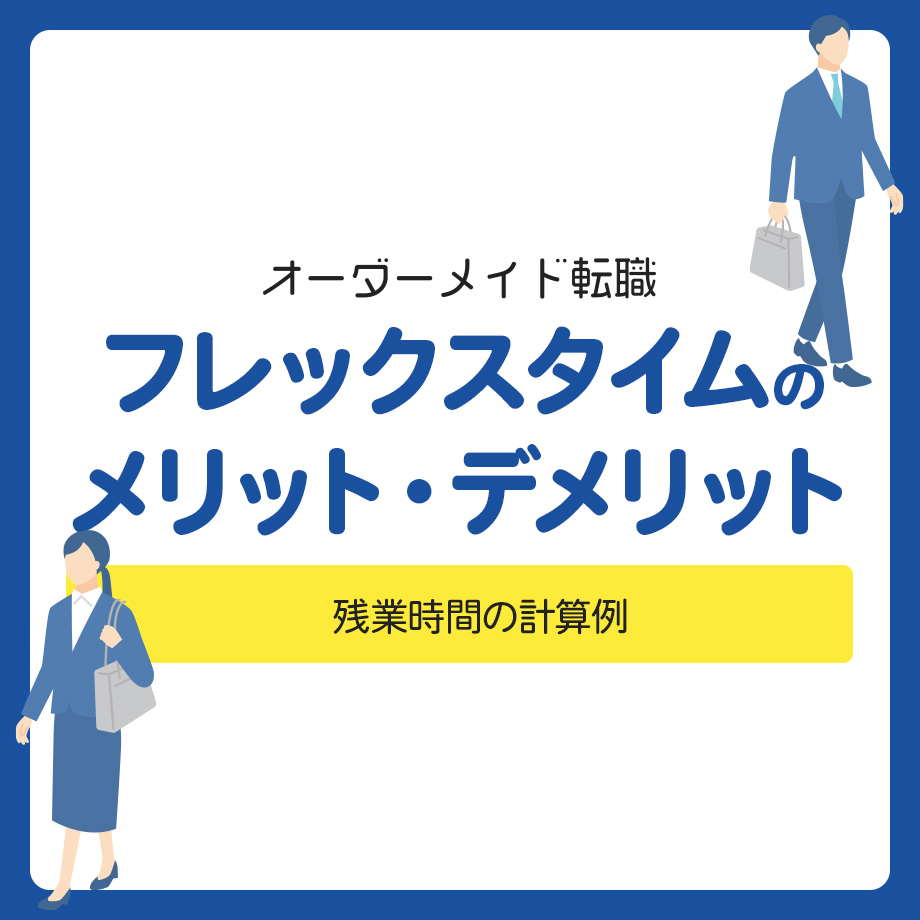
よりワーク・ライフ・バランスを整えやすくなる働き方の一つとして、さまざまな職場で取り入れられているのが、フレックスタイム制と呼ばれる勤務形態です。フレックスタイム制では、出勤や退勤のタイミングを各従業員で柔軟に決められるのが大きな特徴。実際に勤務する時間帯を自由に調整できることから、従業員の働きやすさに配慮する制度として、効果的に活用している企業も多く見られます。そこで今回は、フレックスタイム制の働き方によるメリット・デメリットをはじめ、勤務時間のルールや残業の考え方などを解説します。
フレックスタイム制では各従業員で出退勤時間を調整できる
フレックスタイム制は、冒頭にも出てきたように、従業員自身で勤務時間を柔軟に設定できる社内制度を指します。通常であれば、例えば「9時~18時」というように、決められた時間帯で各従業員が同じように勤務するのが一般的でしょう。その一方で、フレックスタイム制なら、自分の出勤したい時間帯を自由に決めて勤務できるのが基本です。
またフレックスタイム制では、日ごとに異なる勤務時間帯になっても問題ありません。「今日は10時に出るけれど、明日は早めに帰りたいから8時にしよう」などのように、自分の希望によって調整できる勤務形態です。このようにフレックスタイム制は、各従業員のより働きやすいスタイルを実現する制度でもあります。
フレックスタイム制の勤務形態は大きく分けて2種類

フレックスタイム制の導入方法は、企業側の判断で決められるため、具体的な運用の仕方やルールは各社によって異なります。ちなみにフレックスタイム制で設定できる勤務形態としては、大きく分けると、次のような2種類になります。
コアタイム制
1日のうち、一定の時間帯に限って、全員が必ず出勤するコアタイムを設定する勤務形態です。労働基準法では、1日8時間を実働時間の上限とされているため、その範囲よりも短いコアタイムを設けるのが原則。ちなみにコアタイム以外の自由に出勤・退勤ができる時間帯は、フレキシブルタイムと呼びます。
仮に「11時~15時」がコアタイムになっている際には、その前後で、出勤・退勤の時刻を調整して勤務します。なおこのコアタイムのケースでは、出勤は遅くても11時、退勤は早くて15時の範囲なら、勤務時間帯を自由に調整できます。場合によっては、コアタイムの時間帯のみの勤務でも問題ありません。なおコアタイムは、日ごとで変動させたり、分割させたりも可能です。
スーパーフレックス制(フルフレックス)
コアタイムなどの固定した勤務時間を設けずに、出勤・退勤時刻の制限なく働けるのがスーパーフレックス制です。必ず出勤しなければならない時間帯がなく、コアタイム制よりも、自由度の高い働き方ができるのも特徴。各企業の運用ルールにもよりますが、場合によっては24時間いつでも勤務できる例もあります。もしくは「7時~22時の間でスーパーフレックス」などのように、ある程度の範囲を設定して、自由に出勤・退勤ができる仕組みにしているケースも見られます。
フレックスタイム制の働き方で得られるメリット

フレックスタイム制では、自分の働きやすい時間帯に調整して勤務できるのが大きな魅力です。では実際に、フレックスタイム制によって自由度の高い勤務スタイルを実現できることで、どのようなメリットが得られるのか見ていきましょう。
プライベートの都合に応じた勤務時間で働ける
なかにはコアタイムによる一部制限のあるケースも見られますが、基本的には各従業員の事情に合わせて、それぞれで異なる時間帯に勤務できます。例えば保育園の送り迎えや介護で、特定の時間帯で出勤するのが難しかったり、日ごとに勤務のタイミングを変える必要があったりする場合など。フレックスタイム制なら、都合に応じて自由に調整しながら働きやすく、家庭との両立などもしやすいメリットがあります。その他にも、「通院で早めに上がる必要がある」「資格取得に向けた通学時間を確保したい」など、さまざまな状況を考慮しながら勤務時間を変動させることが可能。プライベートの予定も優先しながら、柔軟な働き方がしやすいのも特徴です。場合によっては、「通勤ラッシュをなるべく避けたい」など、ストレスの少ない希望の働き方につながりやすい利点もあります。
業務の状況に合わせて効率的に勤務できる
場合によっては一般的な日中の勤務時間ではなく、日ごとに業務が集中する時間帯が異なり、夕方以降などの変則的なタイミングで作業が忙しくなるなどのケースも。そうした際にフレックスタイム制により、業務量が増えやすい時間帯に出勤できるようにして、より効率的に仕事を進めやすくできるのもメリットです。手の空く待機時間を省くことで、余計な残業を減らせる利点もあります。前述にもあるようなプライベートの予定はもちろん、業務状況に応じて、無駄な時間がないように調整した働き方も可能です。
ライフステージの変化にも対応しやすく長く勤続できる
フレックスタイム制なら、勤務時間を柔軟に調整できるため、労働条件にともなう離職を防げる可能性も高くなります。例えば育児など家庭の事情から、固定の勤務時間で働くのが難しい場合でも、フレックスタイム制で柔軟に調整すれば辞めずに続けられるケースもあるでしょう。このように在職中にライフステージが変わっても、フレックスタイム制によって労働条件に柔軟性があれば、従業員自身で生活環境に合わせた働き方を実現できます。
フレックスタイム制で注意しておきたいデメリット
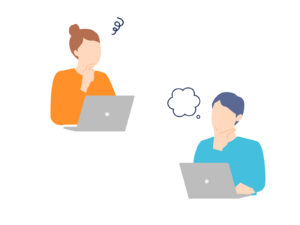
フレックスタイム制では、通常とは少し異なる特殊な勤務形態から、業務が進めづらくなる一面もあります。では実際に、フレックスタイム制で気を付けておきたいデメリットも整理しておきましょう。
しっかりとした自己管理が必要
自分で調整しながら出勤・退勤時刻を設定する必要があり、決められた労働時間数で勤務したり、問題なく業務が片付けられたりできるような自己管理が求められます。勤務時間が固定されていない分、自分自身できちんと生産性やモチベーションを維持できるように、効率面も考慮しながら業務を進めていくことも重要。自由度の高い働き方ができるからこそ、しっかりと自律しながら仕事に励めるような意識を持っておくことも大切です。
周囲とのコミュニケーションが取りづらい
フレックスタイム制では、個人の自由に出勤・退勤時刻を決められるため、周りと勤務時間が合わない場合もあります。そうなると、周囲とコミュニケーションを取る機会がうまく作れず、意見交換や情報共有がしづらくなる一面も。また自分の勤務時間と、担当の取引先との稼働のタイミングがずれてしまうと、やり取りがスムーズに進みづらくなる可能性も考えられます。いずれにしてもこまめに連携が取れるように、社内の連絡ツールなどを活用しながら、必要に応じて対処できるように工夫していくことも重要です。
フレックスタイム制における残業時間や手当はどう計算する?
通常の固定勤務では、基本的には「1日8時間・週40時間」を上限として所定労働時間を設ける必要があり、それを超えて働いた分には割増賃金を支払うルールがあります。もちろん「1日8時間・週40時間」に満たなかったとしても、元々決められた所定時間以上に勤務した場合には、割増賃金はないものの基本給分の残業代が生じます。
こうした前提を踏まえて、フレックスタイム制でも所定労働時間を超えて勤務すれば、当然ながら残業代が発生します。さらに通常の固定勤務と同様に、フレックスタイム制でも、各従業員に課すことができる労働時間には法律上の規定もあります。ではこうした原則があることを念頭に置きつつ、フレックスタイム制では残業時間や手当はどう計算するのか、以下から順を追って解説していきます。
フレックスタイム制における残業時間の考え方
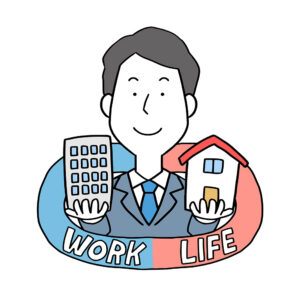
まずフレックスタイム制では、各従業員で勤務時間の調整ができる点から、一定の清算期間を設けたうえで法的な上限を超えた労働が発生した場合に残業とみなします。そのためフレックスタイム制の場合、仮にどこかで1日8時間や週40時間を超える勤務になったとしても、即時に残業とみなされるわけではない点には注意が必要。あくまで清算期間における総労働時間数をもとに、残業時間が発生しているかどうか算出されます。
なおフレックスタイム制の清算期間として設定できるのは、3ヶ月が上限です。ちなみに一般的なフレックスタイム制の清算期間は、1ヶ月単位もしくは2~3ヶ月となります。
またフレックスタイム制における労働時間の原則としては、清算期間に応じて、次のようなルールが設けられています。
1ヶ月を清算期間とした場合
1ヶ月を清算期間に設定した際、各従業員の総労働時間数は、週平均40時間以内に収めるのが法律上の原則です。そこで各従業員の所定労働時間にできる総数の上限は、次のような計算式から算出されます。
週の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数(28日~31日)÷7日間
具体的な数値にすると、清算期間の暦日数ごとの上限は、以下のように計算できます。
- 31⽇/177.1時間
- 30⽇/171.4時間
- 29⽇/165.7時間
- 28⽇/160.0時間
1ヶ月を清算期間とするフレックスタイム制においては、総労働時間数が上記を超過する際に、法定外の勤務として割増賃金が付くようになります。
2~3ヶ月を清算期間とした場合
1ヶ月を超える清算期間を設けるケースでは、フレックスタイム制の総労働時間の上限として、次のような2つのルールが決められています。
- 清算期間全体の総労働時間の週平均40時間未満
- 1ヶ月おきの労働時間の週平均50時間未満
つまり清算期間全体では週平均40時間を超えてはならず、なおかつ月ごとの労働時間は、週平均50時間以内に収まるように勤務させるのが原則です。上記のルールのどちらかでも外れる勤務が発生した場合には、法定外労働として割増賃金が生じます
フレックスタイム制での残業時間の計算例

では実際にフレックスタイム制で残業時間が発生するパターンや、具体的な数値を使った計算方法の事例も見ていきましょう。
1ヶ月を清算期間とした場合
仮に4月で考えるなら、清算期間の暦日数は30日となるため、総労働時間数の上限は177.1時間。1ヶ月の清算期間で合計した勤務時間において、177.1時間を超過した分は、法定外労働として割増賃金が発生します。
ちなみに同じく4月を例として、1ヶ月の総所定労働時間を「170時間」と設定している場合。仮に合計175時間の勤務をした際には、5時間分は残業になるものの、法定外労働にはなりません。そのため割増賃金ではなく、基本給の時給×超過時間数分の残業代のみ、発生することになります。これは法定労働時間数の上限となる177.1時間を超えないため、割増賃金の付かない残業代が支給されます。
3ヶ月を清算期間とした場合
4月~6月を清算期間として、どのように残業時間や法定外労働が発生するのか、具体的な数値を当てはめながら計算してみましょう。
ではまず4月~6月を清算期間とすると、全体における総労働時間数の法定内の上限は、どれくらいになるのか算出します。
大前提として4月~6月の総暦日数(91日間)に対して、法律上の上限とされるのは、週平均40時間以内になる総労働時間数です。具体的には、次のように計算していきます。
週の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数(91日)÷7日間
=520時間(=4月~6月の法定内労働の上限時間数)
そして次に、4月・5月・6月それぞれの月ごとにおける、総労働時間数の法定内の上限を算出してみます。法律上のルールでは、各月で週平均50時間以内になる総労働時間数が上限となっているため、次のように計算できます。
週の法定労働時間(50時間)×清算期間の暦日数(30日)÷7日間
=214.2時間(=4月、6月の法定内労働の上限時間数)※小数点第二位以下切り捨て
週の法定労働時間(50時間)×清算期間の暦日数(31日)÷7日間
=221.4時間(=5月の法定内労働の上限時間数)※小数点第二位以下切り捨て
4月/214.2時間
5月/221.4時間
6月/214.2時間
ちなみに1ヶ月を超える清算期間を設定した場合、先ほども出てきたように、法定外の割増賃金は以下の2種類で発生することになります。
- 清算期間全体で週平均40時間以内の総労働時間から超過した分
- 1ヶ月おきの総労働時間で週平均50時間以内から超過した分
では実際に法定外の割増賃金が生じる残業時間の事例として、前述の4月~6月を清算期間にしたケースを挙げて、具体的な数字を当てはめてみます。
仮に、4月・5月・6月の総労働時間数が以下のようになったとしましょう。
4月/220時間
5月/150時間
6月/160時間
4月~6月の合計/530時間
ここまでに出てきたルールを当てはめていくと、それぞれで次のような法定外の労働時間数が発生したことになります。
4月/5.8時間(220時間-214.2時間)※週平均50時間以内を超えた分
5月/残業なし
6月/残業なし
4月~6月の合計/10時間(530時間-520時間)※週平均40時間以内を超えた分
総合すると上記のケースでは、4月終了時点で5.8時間分、3ヶ月の清算期間時点で10時間分の割増賃金がそれぞれ支給されます。
では仮に所定労働時間として、次のようにすべて法定内の範囲で発生している場合。もし所定労働時間を超える勤務をしたのであれば、割増賃金はないものの、基本給の時給×超過時間数分の残業代が発生します。
<所定労働時間>
4月/170時間(214.2時間未満)
5月/175時間(221.4時間未満)
6月/170時間(214.2時間未満)
4月~6月の合計/515時間(520時間未満)
<実労働時間>
4月/172時間(2時間超過分の残業代)※割増なし
5月/178時間(3時間超過分の残業代)※割増なし
6月/170時間(残業代なし)
4月~6月の合計/520時間(4月・5月時点で残業代が支給されるなら、清算時の残業代はなし)
ここまでに出てきたように、特に2~3ヶ月を清算期間とするフレックスタイム制では、残業時間の考え方や計算方法として複雑なルールがあるので注意しましょう。
まとめ
フレックスタイム制は、勤務時間をフレキシブルに変動させながら、従業員自身の働きやすいスタイルで仕事ができる仕組みです。プライベートや業務状況などに応じて、柔軟に勤務時間を調整しながら、自分自身で希望どおりの働き方にできる効果が見込めます。ただし一方で自由な働き方ができる分、自分なりに業務がスムーズに進むように工夫することも必要です。またフレックスタイム制において、残業とみなされる労働時間の考え方や計算方法には、いくつもの複雑なルールもあります。ぜひ本記事も参考にしながら、どのような場合に残業が発生するのか、具体的な働き方もイメージしてみましょう。
