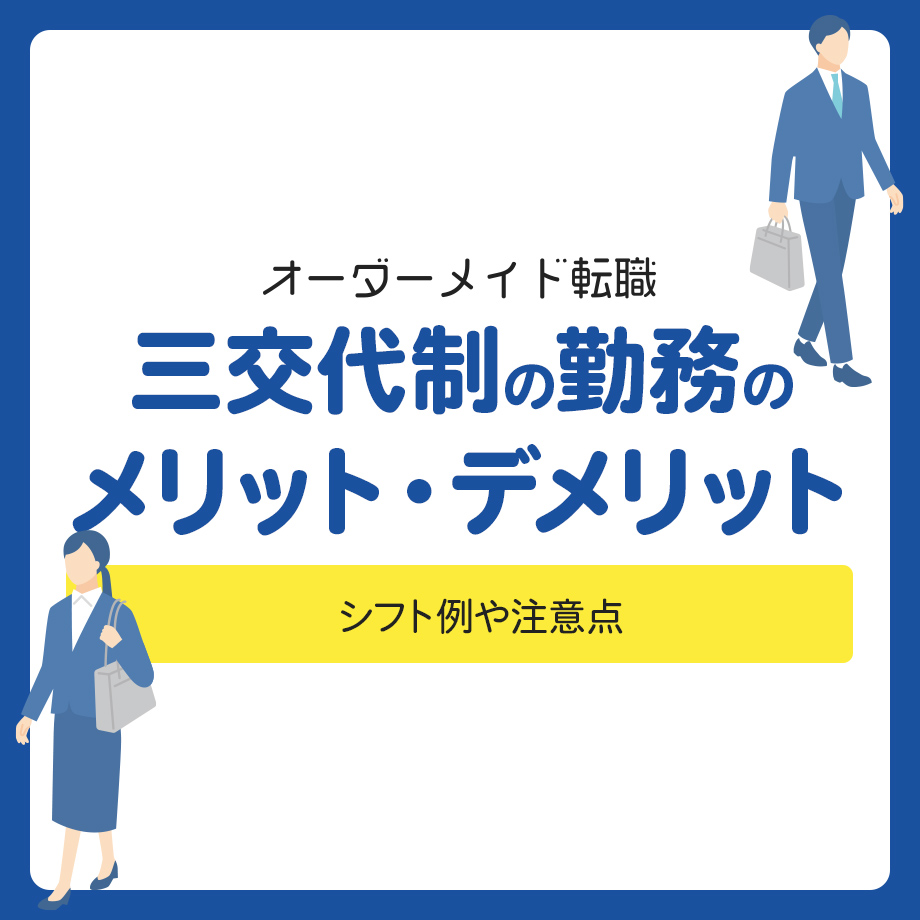
例えば事務職などのオフィスワークでは、朝から夕方までの日中に出勤する、固定された勤務形態が一般的です。ただし業種や職種によっては、時間帯ごとに交代して出勤するシフト制になるケースもあり、なかでも24時間稼働が必要な業態では三交代制と呼ばれる勤務形態も見られます。そこで今回は、この三交代制の勤務形態に注目し、働き方のメリットやデメリットを解説。あわせて、よくある代表的なシフト例や、実際に働くうえで注意したいポイントなどもご紹介していきます。
三交代制は3つの時間帯でシフトを組む勤務形態
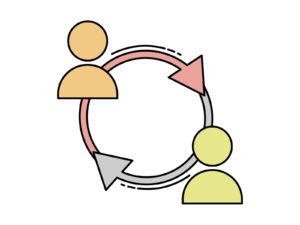
三交代制とは、24時間を3つの時間帯に分けたシフトを設定し、各従業員が入れ替わりながら出勤する勤務形態を指します。
労働基準法では、基本的に「1日8時間・週40時間」を各従業員の勤務時間の上限としており、それ以上の労働を課すことはできません。とはいえ、例えば緊急時に備えた24時間体制の稼働が求められる病院や福祉施設などでは、深夜や早朝も含めて人員を配置しておく必要があります。こうした業態において各従業員で異なる時間帯に出勤し、常時稼働できる体制として取り入れられやすいのが、三交代制です。
三交代制のシフトが導入されやすい業態としては、前述にもあるような病院や福祉施設をはじめ、次のような例が挙げられます。
- 医療・福祉:病院(医師、看護師)、介護施設(現場職員)
- 製造業: 24時間稼働が必要な工場、製鉄所、製紙工場 など(機械オペレーター、ライン作業 他)
- 小売・サービス業:24時間営業のコンビニや飲食店 など(店舗スタッフ、サービススタッフ、調理スタッフ 他)
- 宿泊業:ホテル(フロント、レストラン部門の調理師 他)
- 警備業:24時間保安が必要なビルや公共施設・商業施設 など
- インフラ関連:水道・電気・ガス・鉄道・道路の整備や工事 など
- その他:消防署・警察・自衛隊などの一部公務員
なお三交代制では、大まかには以下のような時間帯で勤務するケースが多く見られます。
- 日勤(早番):朝~夕方(例/9時~18時、8時~17時、7時~16時 など)
- 準夜勤 (前夜勤、中番):夕方~深夜(例/16時~翌1時、17時~翌2時 など)
- 夜勤(深夜勤、遅番):深夜~早朝(例/22時~翌7時、23時~翌8時、24時~翌9時 など)
上記のような3つの時間帯で従業員を入れ替えることで、労働基準法を守りつつ、24時間無休で稼働できる業態を実現しています。
三交代制の働き方で得られるメリット
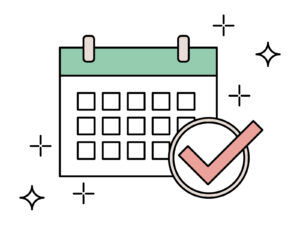
三交代制を取り入れる大きなメリットとして、従業員を雇用する側には、労働基準法の規定内で24時間稼働の体制を確保できる効果があります。さらには実際に働く従業員側にも、三交代制の勤務形態によって期待できる利点はいくつか存在しています。では三交代制の働き方をすることで、具体的にどのようなメリットがあるのか、以下から詳しく見ていきましょう。
深夜帯の割増賃金で給与が比較的高くなりやすい
労働基準法では、「22時~翌5時」の時間帯で勤務させる際には、通常の基本給に加えて必ず割増賃金を支払うことが義務化されています。ちなみに「22時~翌5時」の時間帯で勤務した場合、2.5割以上の割増賃金を支給するのが法律上のルールです。
こうした深夜割増の規定があることから、三交代制の勤務形態では、毎月の給与が高めになりやすいメリットがあります。例えば22時以降の深夜までかかる、準夜勤や夜勤のシフトが入っていれば、日勤だけの勤務に比べて割増賃金分は多めに稼ぐことが可能。日勤と同じように8時間働いたとしても、夜勤なら割増賃金が加算される分、効率的な収入アップに期待できます。
残業が少なく仕事後の予定が立てやすい
一般的な固定シフトで、どの従業員も同じ時間帯に退勤する勤務形態では、例えば急ぎの作業などが残ったら自分で残業して対応しなければならない場合も多々あります。一方、三交代制であれば次の時間帯に出勤するメンバーに任せるなどもでき、残業になりにくいのがメリットです。次のシフトに引き継ぎながら業務を進められるので、きちんと決まった時間帯で働きやすいのが大きな利点。また残業になるケースが少ないため、例えば日勤で仕事終わりからプライベートの予定を入れたい時にも、仕事の都合が気になりづらく安心です。
平日の昼間の時間を使える可能性が高い
シフトにもよりますが、例えば準夜勤や夜勤の出勤前など、日中の時間をプライベートに使える場合も多く出てきます。そうすると平日の昼間に動けるケースもあり、役所・病院・銀行などでの用事が済ませやすいことも。もちろん日中を睡眠時間に充てる必要があることも少なくありませんが、タイミング次第では、平日の日中をうまく使える方法も考えられます。
また三交代制で、24時間年中無休稼働の業態では、平日休みになるシフトも多々出てきます。こうした平日休みを活用すれば、週末に混みやすいレジャースポットなど、比較的空いている機会で楽しめるのもメリットでしょう。
通勤ラッシュに被らないシフトがある
三交代制では、一般的な出勤・退勤時間と異なるシフトになることも多く、通勤ラッシュのタイミングと被らずに職場との行き来ができるケースも少なくありません。電車通勤だと使用する路線にもよりますが、満員電車や渋滞に巻き込まれずに、移動のフラストレーションなく通える日が出てきやすいのもメリットです。毎日の通勤ラッシュを避けられるだけでも、心身の負担を軽減しやすく、ストレス感を抑えやすいのは大きな利点でしょう。
三交代制で気を付けておきたいデメリット

三交代制では、一般的な固定勤務とは大きく異なるワークスタイルになることから、気を付けておきたいデメリットもいくつか出てきます。特に三交代制の働き方においては、次のような一面があることも想定しておきましょう。
慣れるまでに時間がかかる
三交代制で、日ごとに出勤時間が変わる勤務形態の場合、はじめのうちは体がなかなか付いてこないケースも。三交代制でもきちんとリフレッシュできるような、自分なりの生活リズムのパターンが見つかるまでは、疲れが溜まりやすいなどの一面もあります。例えば転職で固定勤務から三交代制に変わった時には、今までの生活習慣を変えていくのが難しく、働き方に慣れるまで少し時間がかかってしまうことも想定されます。体力的な心配があるうちは、なるべく睡眠時間を長めにしたり、早く寝つけるように対策したりなど、しっかりと疲れが取れるように工夫しておく必要があるでしょう。
身体的・精神的なストレスを大きく感じやすい可能性がある
前述にもあるように、日ごとに働く時間が異なると、一定の生活リズムを保つのが難しい部分もあります。こうした不規則な生活から、心身に大きな負担がかかってしまうケースも。また準夜勤や夜勤のシフトでは、深夜遅い時間の食事になったり、コンビニなどの簡単なメニューで済ませたりする場合も多く出てくるでしょう。さらに毎日の就寝時間も変わってくるため、なかなか眠れないなど、睡眠の質が下がってしまうこともあります。安定した働き方がしづらい分、身体的・精神的なストレスを感じやすく、体調を崩してしまう可能性が高い点にも注意が必要です。きちんと体調管理ができるように、配慮しておくことも重要です。
家族や友人との生活時間が合わせにくい一面がある
不規則な働き方になりやすい三交代制では、周りの家族や友人が一般的な固定勤務だと、生活時間が合わせづらい難点もあります。またお子さんがいる場合には、学校などに通う時間は日中になるので、三交代制で準夜勤や夜勤が入ってしまうと顔を見る機会が減ってしまうことも。さらに自分と周りとの勤務形態が変わってくると、プライベートの予定が立てづらかったり、生活時間のずれから睡眠の妨げなどのストレス感が生じやすくなったりするケースもあります。特に同居の家族がいる際には、生活時間が合わせにくい部分の理解も得られるように、あらかじめしっかりと相談しておくのが無難でしょう。
シフトによっては通勤に公共交通機関が使えない場合も
例えば準夜勤や夜勤のシフトでは、出勤や退勤の時間帯で、公共交通機関がストップしていることも珍しくありません。こうした変則的な通勤時間にも対応できるように、場合によってはマイカー・バイク・自転車や、徒歩で通える職場を選ぶ必要も出てきます。もちろん通勤手段にきちんと配慮されている職場もあるので、例えば送迎バスやタクシー代の支給など、問題なく通えそうな待遇面があるかどうか確認しておくことも大切です。
三交代制でよく見かけるシフト例の代表パターン
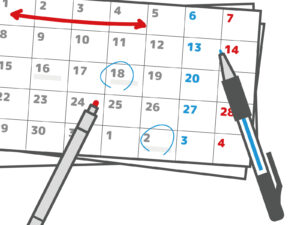
実際の働き方のイメージとして、三交代制でよくある代表的なシフト例についても見ていきましょう。
三交代制のシフト例では、大きく分けると次のような3つのパターンが見られます。
- 1日ごとに出勤時間が変わるパターン
- 週単位や月単位などの一定期間で出勤時間が異なるパターン
- 各時間帯で固定シフトになるパターン
ではそれぞれのパターンで、どのような働き方になるのか具体的に解説していきます。
1日ごとに出勤時間が変わるパターン
基本的には日勤を中心として、週に1~2回程度、準夜勤や夜勤が入るケースが多く見られます。例えば「深夜では待機が多くなる」など、日中と夜間で業務量に差が出やすい業態で、よく取り入れられているのも特徴。なお1週間のスケジュールとしては、次のようなイメージです。
月:日勤(9時~18時)
火:日勤(9時~18時)
水:準夜勤(16時~翌1時)
木:夜勤(24時~翌9時)
金:明け休み
土:休み
日: 日勤(9時~18時)
上記のように、準夜勤や夜勤の前後には、きちんと休息時間が確保できるようなシフトになるのが通常です。もちろん職場にもよりますが、日勤と準夜勤・夜勤の合間に休日を設定して、生活リズムの切り替えがしやすいように配慮される場合も多く見られます。
週単位や月単位などの一定期間で出勤時間が異なるパターン
この場合は、もし週単位なら、日勤・準夜勤・夜勤のシフトが1週間ごとに変わる勤務形態となります。具体的には、次のようなスケジュールのイメージです。
1週目/月:日勤 火:日勤 水:休み 木:日勤 金:休み 土:日勤 日:日勤
2週目/月:休み 火:夜勤 水:夜勤 木:夜勤 金:夜勤 土:明け休み 日:休み
3週目/月:準夜勤 火:準夜勤 水:準夜勤 木:準夜勤 金:明け休み 土:休み 日:日勤
4週目/月:日勤…
週単位のパターンでは、「日勤×週5日+準夜勤・夜勤×週4日」というようなリズムの勤務形態がよく見られます。準夜勤や夜勤では、退勤した翌朝からの明け休みが入ることが多く、上記のようなシフト例になるケースも多数。なお週単位や月単位では、一定期間は同じ出勤時間が続くため、三交代制のなかでも比較的生活リズムが整えやすい特徴もあります。
各時間帯で固定シフトになるパターン
職場としては三交代制となっているものの、従業員ごとの勤務時間帯そのものは固定されているパターンです。本人の希望などに応じて、「日勤選任」「夜勤選任」というように、時間帯で担当を分けて三交代制にしているケースもあります。この場合には、各従業員の生活リズムは一定になるため、安定した働き方がしやすいのも特徴です。
三交代制の働き方で注意しておきたいポイント
ここまでに見てきたように、三交代制では勤務時間帯が一定でない場合が多く、不規則な生活になりやすい一面があります。そうしたなかでも、しっかりと体調管理をして生産性やモチベーションを上げるためには、以下のような点に注意しておくのがベストです。
健康的な食事や睡眠に配慮する
先ほども出てきたように、三交代制では不規則な生活リズムから、心身への負担が大きくなりやすい一面もあります。そこで身体的・精神的なストレスをできるだけ軽減するためにも、基本中の基本ではありますが、日頃から健康的な食事や睡眠に配慮しておくことも大切です。例えば時間帯に関係なく寝つきやすいように、アイマスクや睡眠補助器具などの便利なグッズを用意するなど。また夜勤中で深夜に食べる際には、胃腸への負担を考えて消化にいいメニューを意識するなど、食事に関しても工夫しておくのがおすすめ。食べるメニューが偏ってしまうなど、うまく栄養補給ができないと、体調を崩しやすくなるので注意が必要です。きちんと体調管理ができるように、食事や睡眠の質が下がらないように心がけることも重要です。
無理のないスケジュール管理を意識する
特にプライベートの予定を立てる時などには、もちろん余暇を楽しむのも大事ですが、しっかりと休息時間も取れるように意識しておくことも欠かせません。十分な睡眠時間なども確保できるように、無理のないスケジュールを組むことも重要です。
また不規則な働き方のなかでも、自分のなりに、体調を維持しやすい生活リズムを見つけることも大切。例えば「夜勤がある日は○時頃まで寝ておくと疲れにくい」など、自分に合った習慣を探してみるのも、体調管理には効果的です。自分の働きやすいルーティンに沿った動き方ができるように、日々の過ごし方にも配慮しておくとベストでしょう。なおどうしても体調がすぐれない場合には、シフトの一時的な調整など、勤務形態を相談してみる方法もあります。
まとめ
三交代制は、通常の固定勤務とは大きく異なる働き方ですが、変則的だからこそ得られるメリットも多くあります。とはいえ不規則な働き方になる分、注意しておきたいデメリットもあり、三交代制で勤務する際には十分に考慮しておきたいポイントといえます。三交代制の勤務形態が合っているかどうかは、人によって変わってくるので、ぜひ本記事も参考にしながら自分に適しているか検討してみましょう。
